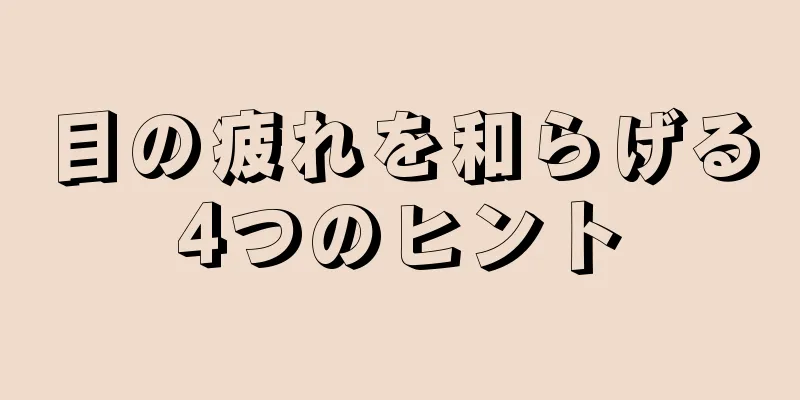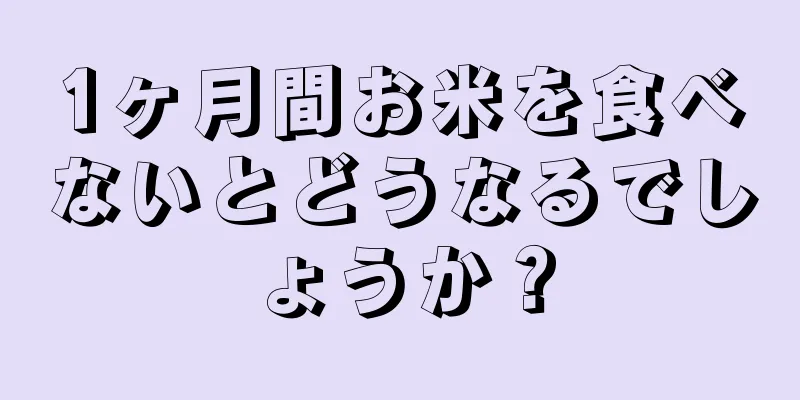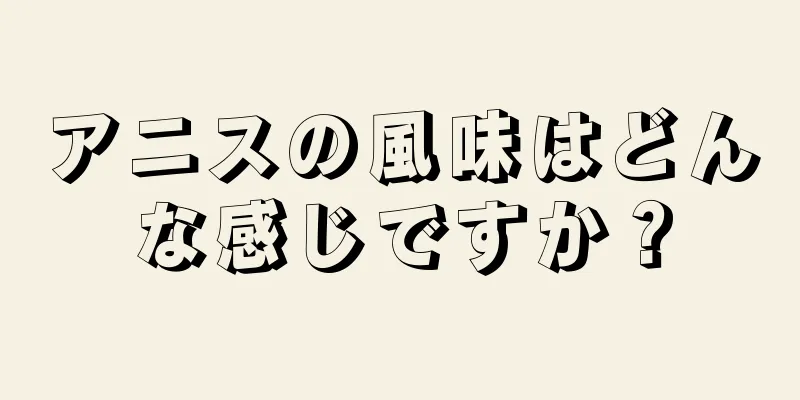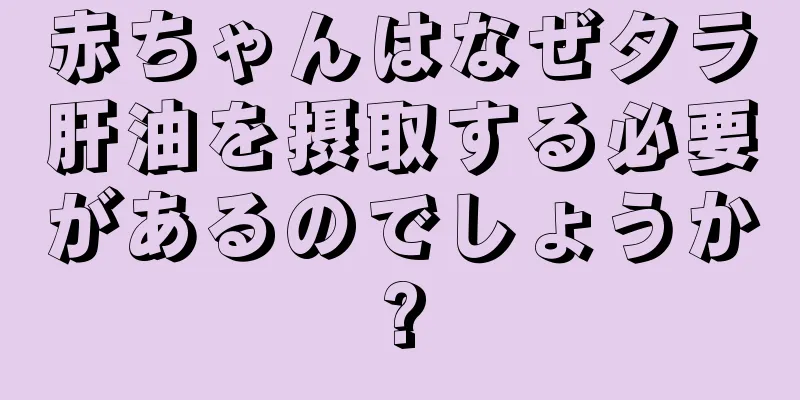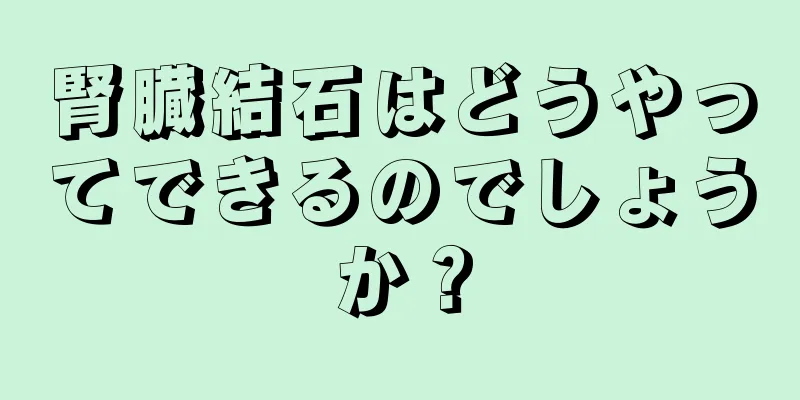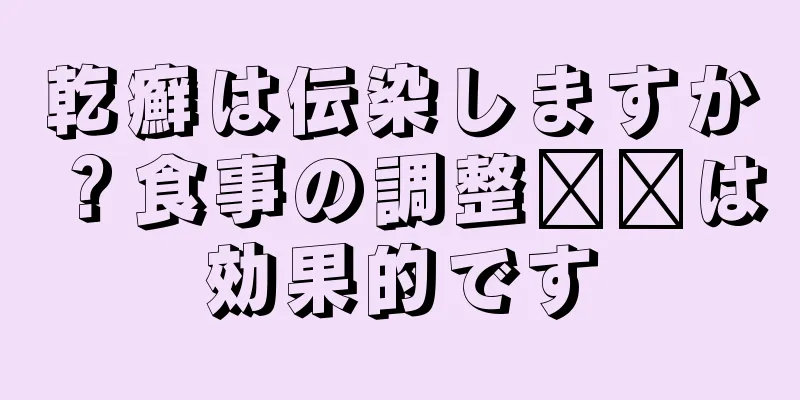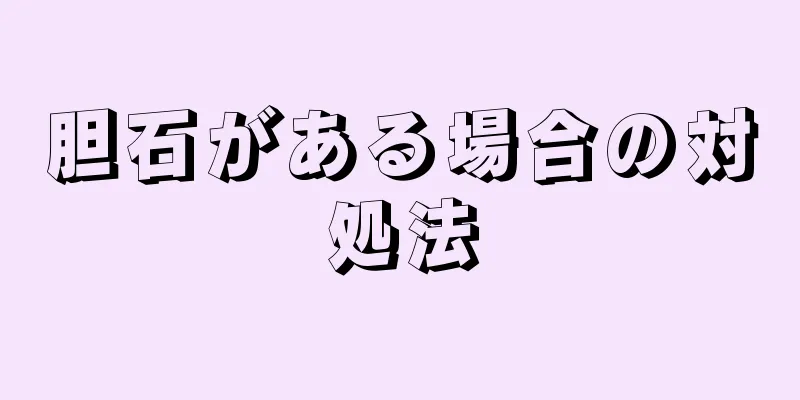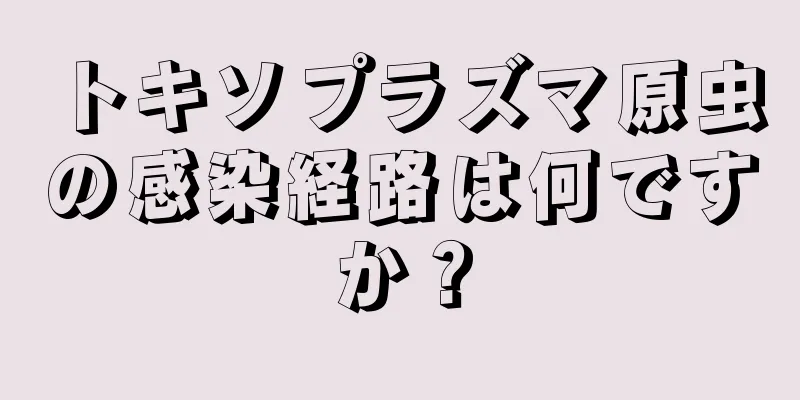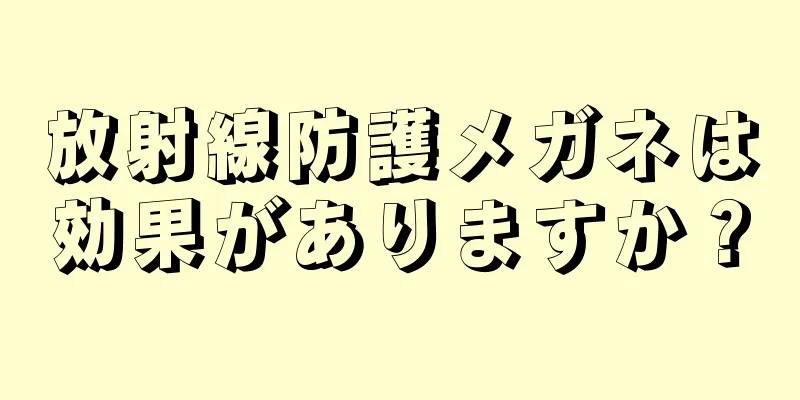肉を焼くとなぜ泡立つのでしょうか?
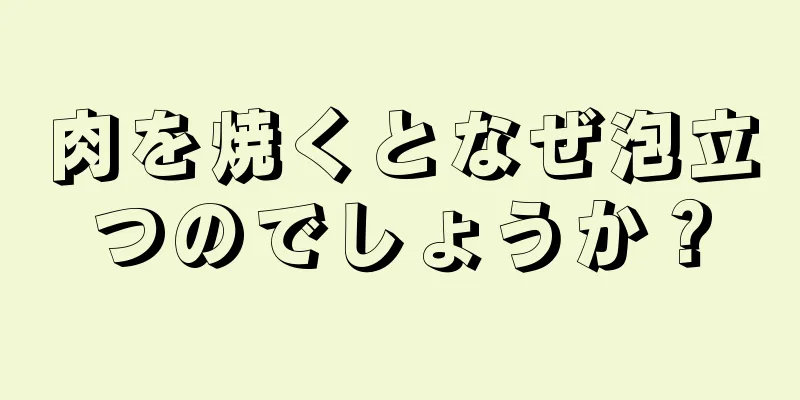
|
肉を調理するとき、煮込む過程でスープに泡がたくさん浮いて、見た目がとても汚いことに誰もが気づくでしょう。泡を取り除くのは実はとても簡単です。肉を数回洗うか、調理する前にしばらく浸してから、調理する前に湯通しします。こうすると、調理中に泡がほとんど出なくなります。では、肉を焼くと泡が出るのはなぜでしょうか? この泡の層は、肉の毛細血管に残った血液によって形成されます。注意深い友人は、肉の異なる部分を調理したときに生成される泡の量が異なることに気付くでしょう。これは、異なる部分の毛細血管の数が異なるためです。豚の背肉など、模様がはっきりしている肉は、毛細血管が少ないため、残った血が洗い流されやすく、スープを作ったときに泡立ちが少なくなります。しかし、脚や肩などの複雑な模様があり毛細血管が豊富な肉に残った血をきれいにすることは非常に難しいため、スープを作るときに泡が多く発生します。 血液はなぜ加熱すると泡になるのでしょうか? これには血液の成分の分析が必要です。以下では豚の血液を例に挙げて、加熱すると豚の血液が泡立つ理由を説明します。この時点で、泡形成の原理を理解する必要があります。食品の泡は通常、連続液相または可溶性界面活性剤を含む半固体相の泡によって形成される分散系です。下の図の通りです。簡単に言えば、子供がシャボン玉を吹くのと同じ原理であり、卵白を泡立てて泡を作るのと同じ原理です。 豚の血液にはヘモグロビンが豊富に含まれており、新鮮な血液の18.9%を占めていることは誰もが知っています[1]。ヘモグロビンは、安定した泡を形成できる溶解度の高いタンパク質です。豚肉のスープでは、ガスは空気または二酸化炭素であり、連続相は豚肉のスープです。水が沸騰すると、水に溶けていた空気が放出されます。温度が100℃まで上昇すると[2]、ヘモグロビンは変性し、二次、三次、四次構造が破壊されます。その結果、水素結合とジスルフィド結合が開き、ポリペプチド鎖が露出します。ポリペプチド鎖はスープの中の泡に結合し、タンパク質の体積が膨張して泡を形成します。 専門用語をたくさん言った後、実はこの泡の層はヘモグロビンとガスが結合したもので、ヘモグロビンの量が増えて泡が形成されるのです。 分かりましたか?この泡は無害です。ヘモグロビンがどんな形になっても、それは単なるタンパク質です。見た目に騙されないでください。しかし、熟練した食通の観点からすると、この泡の層は魚臭く、味も悪いので、取り除くことをお勧めします。 この泡の層をどうやって取り除くのでしょうか? 1. 材料をきれいな水に十分長い時間浸し、水を数回交換します。 2. スープを作る前に、いくつかの材料を沸騰したお湯で茹で、スープを作る前に冷ます必要があります。 3. 上記の処理を行った後、スープを煮込むと、一部の材料から泡が発生します。この時、ザル(泡をすくうための専用のメッシュスプーンもあります)などの道具を使って、上層の泡をすくい取ります。 |
推薦する
頸椎の異常はどのような病気を引き起こす可能性がありますか?
頸椎の状態が悪いと、胃腸や腹部の膨満感などの問題が起こり、その後に神経反応が起こることが多いため...
食品添加物とは何ですか?
多くの食品には添加物が含まれており、食品の品質、色、香り、味を比較的良好な状態に保つことができます。...
甲状腺結節石灰化の悪化を防ぐ方法
多くの人は甲状腺についてあまり知りません。実際、甲状腺結節が石灰化すると、体に深刻な影響を及ぼします...
ソフトサイコの効果は何ですか?
ミシマサイコは一般的な中国の薬用植物で、地理的分布に応じて南方ミシマサイコと北方ミシマサイコに分けら...
前屈を最速で行う方法
前屈は体の柔軟性を高めるための運動です。学生時代、体育の授業で先生からよく前屈をするように言われまし...
あなたを怖がらせるかもしれない健康に関する8つの噂: 寒いときにお酒を飲む?
黒キノコを定期的に食べると肺がきれいになる長引く煙霧により、肺をきれいにする民間療法も数多く生まれ...
舌が乾燥する原因は何ですか?
特に夏場は口や舌が乾燥することが多いので、舌が乾燥していることに気づく人もいます。これは、夏は暑くて...
遺伝性代謝疾患肝硬変
肝炎は適切な時期に治療しないと、徐々に肝硬変に進行します。脂肪肝や肝炎などの肝疾患が肝硬変に進行する...
脾臓と腎臓の欠乏の症状は何ですか?
脾胃虚寒は、脾胃が弱く、体内の陰寒が比較的強い病気です。一般的には、長期にわたる不規則な食事と頻繁な...
びらんを伴う表在性胃炎の原因は何ですか?
胃炎は胃の重度の炎症です。表在性胃炎は胃炎の一種です。表在性胃炎はびらん症状を伴うのが一般的です。び...
歯の詰まりの問題を解決する良い方法
歯並びが悪い人は骨の多い肉を食べてはいけません。骨が歯に詰まりやすくなります。歯に食べ物の残りが残っ...
キュウリは肌を白くするのでしょうか?
美白方法については、多くの人がとても気にかけていると思います。特に美容を愛する女性の多くは、外的要因...
入れ歯の危険性は何ですか?
現代社会では人々の食に対する需要がますます高まるため、多くの人が仕事の空き時間に食欲を満たすためにさ...
無酸素運動とは何ですか?
運動は身体に多くの利益をもたらし、人々のストレスを適時に解消し、体型の美しさを増すことができるため、...
ひよこ豆の働きや効果、食べ方とは?
ひよこ豆は生活の中でさまざまな用途に使われています。例えば、幼児や高齢者の栄養補助食品として、また病...