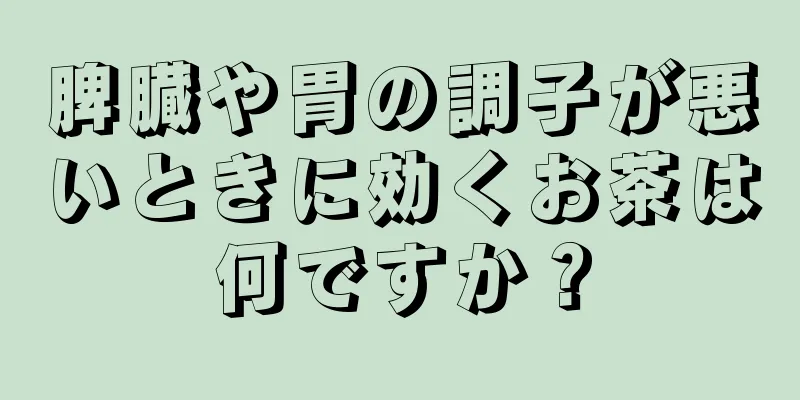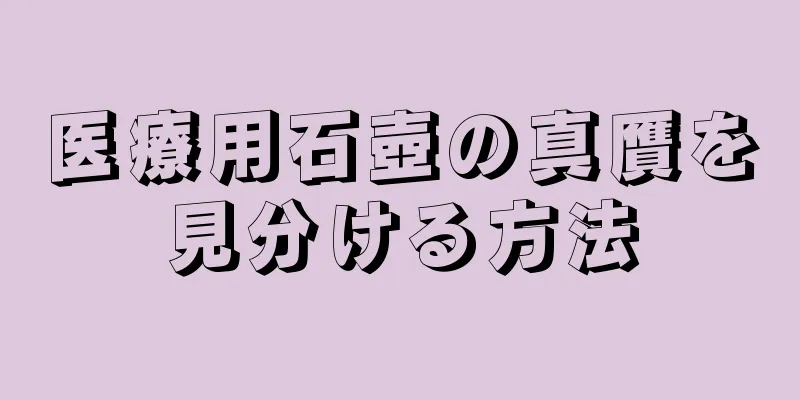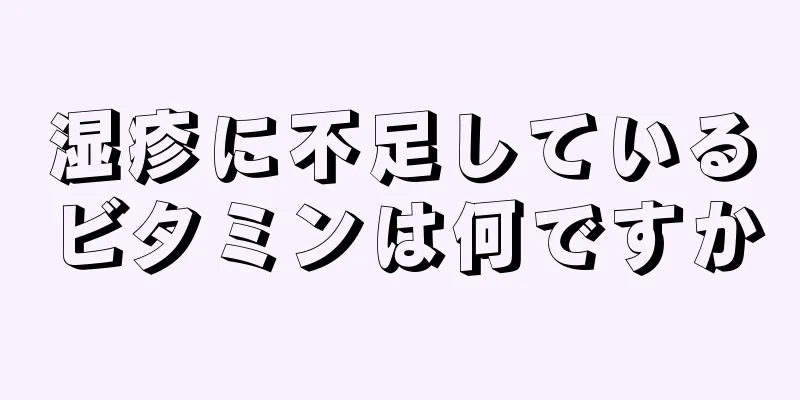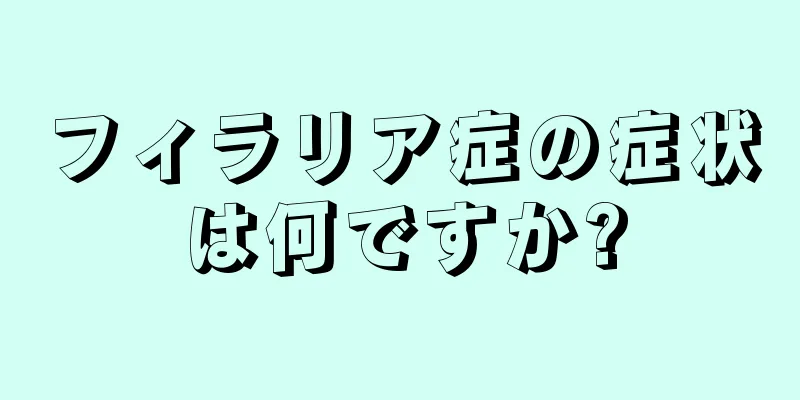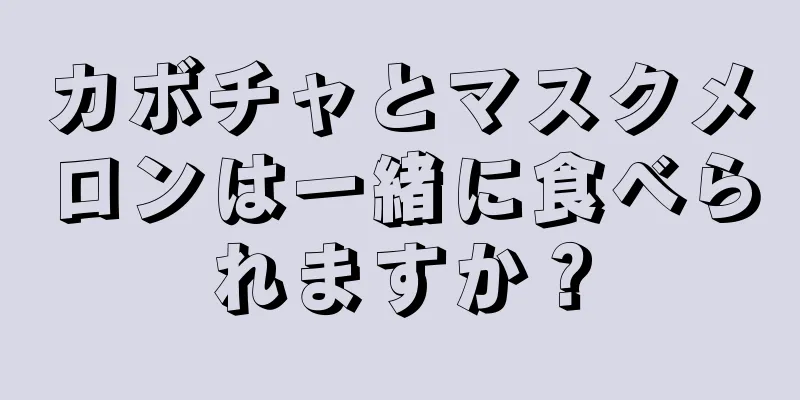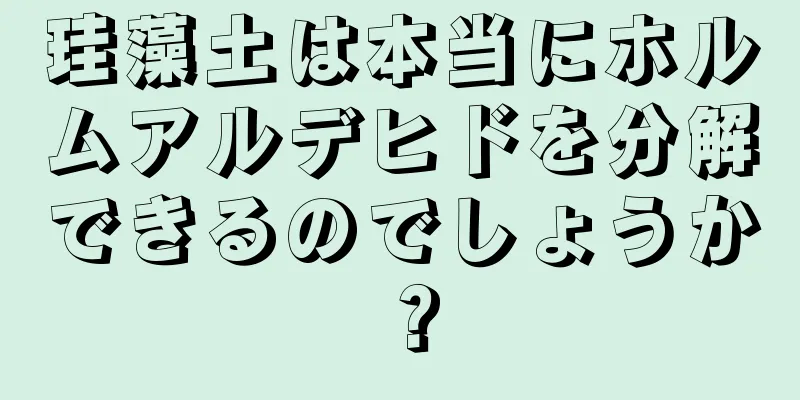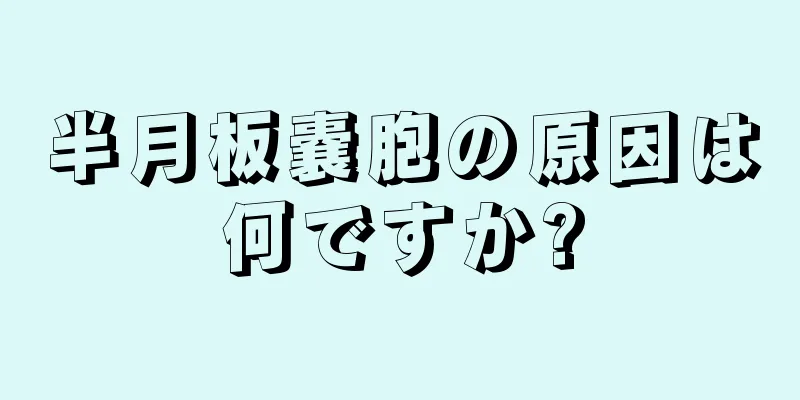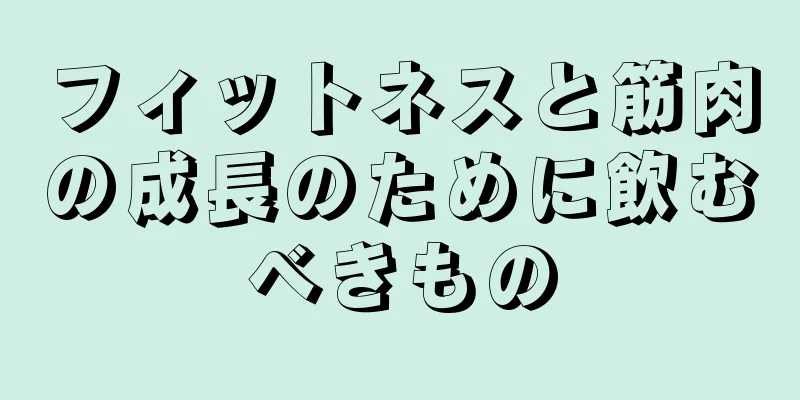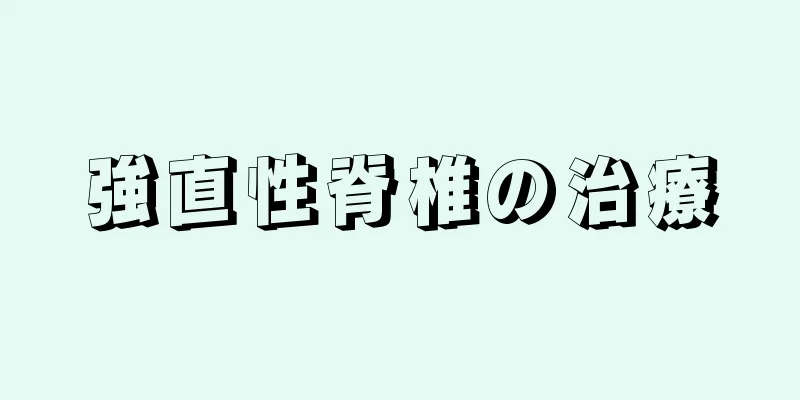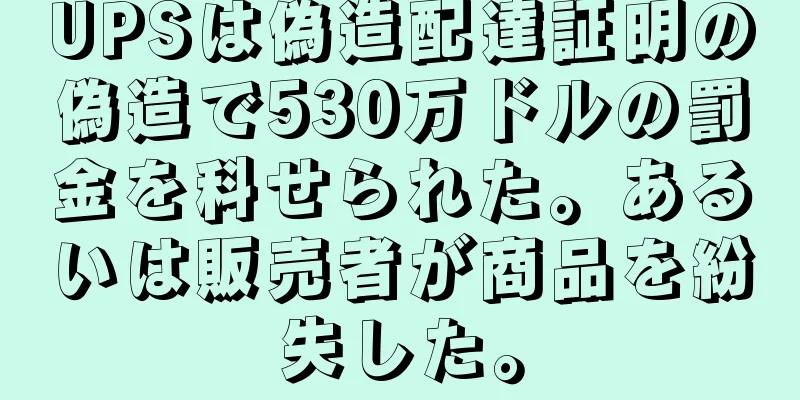感電の後遺症は何ですか?
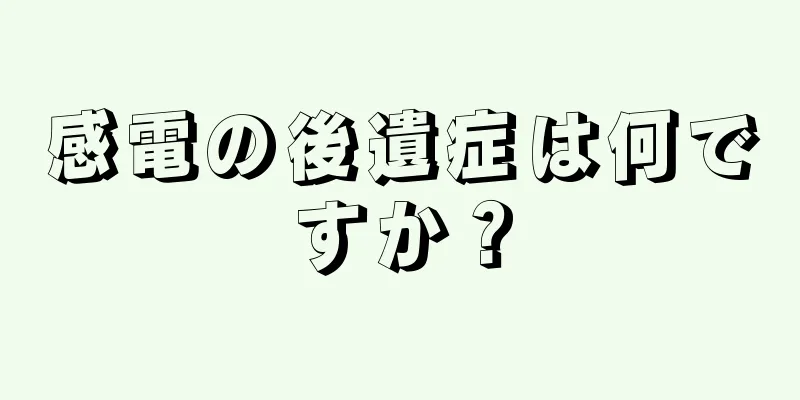
|
感電は主に電流が人体に直接侵入することで発生し、身体に損傷や機能障害を引き起こします。私たちの生活には電気があふれており、電気に関わる仕事に就いている人もたくさんいます。また、事故による感電も時々起こります。感電は身体に影響を及ぼすだけでなく、後遺症も残りやすくなります。では、電気ショックの副作用とは何でしょうか? 以下で詳しく見てみましょう。 1. 電気的昏睡 感電後、患者は短時間の昏睡状態になることが多く、その割合は症例の 20% ~ 50% を占めます。通常は意識が回復します。頭部に損傷がある場合は、短時間の昏睡状態に加えて、患者は混乱したり興奮したりすることもあります。CT 検査では、局所的な脳浮腫が明らかになり、続いて脳軟化がみられることがあります。機能していない部位に発生した場合は局所的な症状は現れず、治療後は回復し、脳に後遺症は残りません。 2. ヘモグロビン尿とミオグロビン尿 適切なタイミングで治療すれば通常は回復しますが、重症の場合は腎臓に一定の損傷が生じます。 3. 無呼吸(仮死状態)、ショック、心室細動 重症患者によく発生します。救助が間に合わなければ、すぐに死亡する恐れがあります。呼吸が止まった後は、呼吸が安定するまで人工呼吸を長時間続ける必要があります。 4. 地域的な現象 傷害部位には入口と出口があり、電流が通る部位に沿って継ぎ目状の筋肉壊死が発生します。骨の周囲の軟部組織壊死がよく見られ、骨や関節の損傷が露出します。重症の場合は頭部に損傷が生じ、穿孔欠損、腹部穿孔欠損、腸管損傷、肺損傷などが生じる場合があります。 5. ジャンプによる怪我 上肢が感電すると、手首、肘の前部、脇の下に傷害が起こることが多い。これは、感電時に筋肉が刺激されて収縮し、上肢が屈曲することで手首、肘の前部、脇の下に新たな短絡が形成されるためと考えられる。 6. 血管壁の損傷 血液は良導体であるため、電流が容易に通過し、血管壁に損傷を与え、血管塞栓症や血管破裂を引き起こし、二次的な局所組織壊死や四肢壊死を引き起こします。 7. 創傷の特徴 局所組織の壊死が遅れて起こり、傷は深くなり拡大し続けます。一般的には、「口は小さく、お腹は大きく、頻繁に変化します。入院したときはこのように見えますが、数日以内にまた変化します。」として知られています。その原因は、電気ショックによる局所の二次的血管塞栓、破裂、二次的感染、間質組織の壊死と密接に関係しており、また、電流や強電界による局所組織細胞膜の損傷や組織壊死の進行とも関係しています。 以上が感電後遺症についての紹介です。皆様の理解の一助になれば幸いです。電気は私たちの生活に欠かせないものです。電気を使用する際には、身体に重大な危害を及ぼすことをできるだけ避けるために保護対策を講じる必要があります。また、感電した場合は、重篤な後遺症を避けるために積極的に治療を受ける必要があります。 |
<<: ポリエンホスファチジルコリン注射の投与量はどれくらいですか?
推薦する
太ると足も太くなる
人間の体は太っているわけではありませんが、体重が増えるたびに、最も目立つ部分である脚に現れます。ほと...
皮膚アレルギーがある場合、ヘーゼルナッツを食べてもいいですか?
ナッツは間違いなくスーパーの棚のベストセラーです。スナックとして、活発な口を満たすことができます。強...
心臓血管系に問題がある場合は何を食べればよいでしょうか?
現代人は肉や魚をたくさん食べることに慣れており、肉なしでは生きていけません。体は長期間肉を食べること...
マットな靴から油汚れを落とすにはどうすればいいですか?
外出するときは、誰もがきちんとした服装をし、きちんとした清潔な服を着て、靴も比較的清潔です。しかし、...
血管造影とは
現代の医療技術の急速な発展に伴い、さまざまな先進的な医療診断・治療技術が登場し、人々の健康をしっか...
精神状態が悪い場合の対処法
悪い精神状態とは、ストレスや疲労などの原因で悪い精神状態になることを指します。悪い精神状態が起こった...
アロエベラの治療法と用途は何ですか?
アロエベラは一般的な天然緑植物です。生活環境を美しくするだけでなく、美容やスキンケア効果も非常に優れ...
尿はなぜアンモニア臭がするのでしょうか?
正常な尿は透明で、臭いも非常に弱いです。尿路が感染したり、膣が炎症を起こしたりすると、尿は強いアンモ...
ベイベリーの酸味を取り除く方法
ヤマモモは食欲をそそる果物ですが、酸味が強く、多くの人はそれを受け入れられませんが、それでも食べたが...
衣服についた油汚れを落とす方法
女友達が母親になった後、子供が病気になる可能性に直面することに加えて、最も面倒なことは子供の服を洗う...
ホワイトパレスマッドネスで何を食べるべきか
白斑は比較的よく見られる皮膚疾患で、主な症状は後天的な皮膚の喪失で、皮膚に斑点が現れます。多くの人は...
ウールのコートが毛玉になったらどうすればいい?
一般的に、ウールのコートは長期間着用すると毛玉ができてしまいます。主な原因は生地と摩擦です。生地はウ...
Amazon が複数サイトのレビューの統合をテストし、クレームポリシーを調整します。
アマゾンは複数のサイトからのレビューを統合するテストを実施 12月17日、Amazonは世界中の消費...
タンポンの使い方
生理中にタンポンを使用する女性の友人が増えていますが、その使い方についてはまだよくわかっていません。...
足に赤い斑点ができる病気は何ですか
人生の中で、多くの人がさまざまな皮膚病に悩まされることがよくあります。皮膚病の原因は、体のタンパク質...