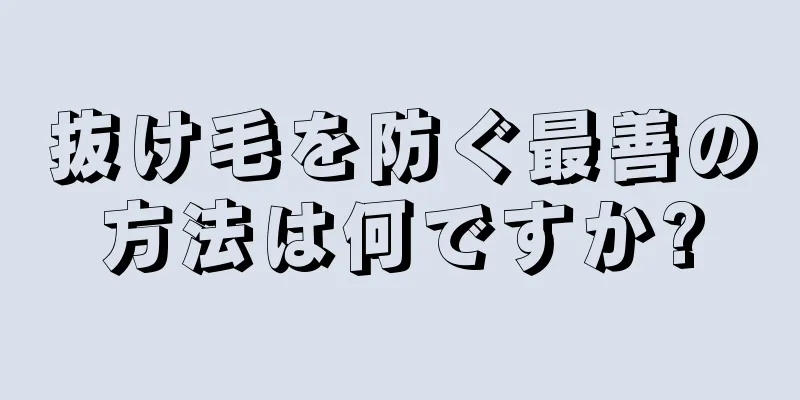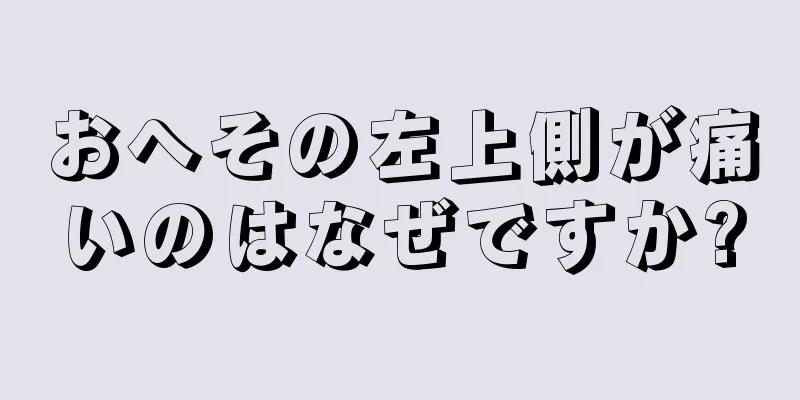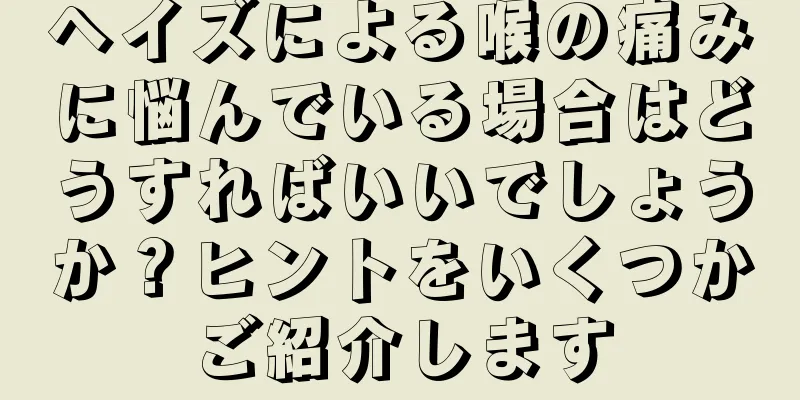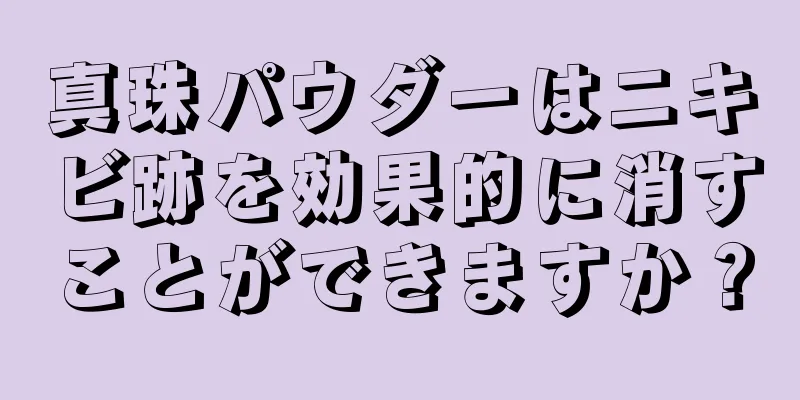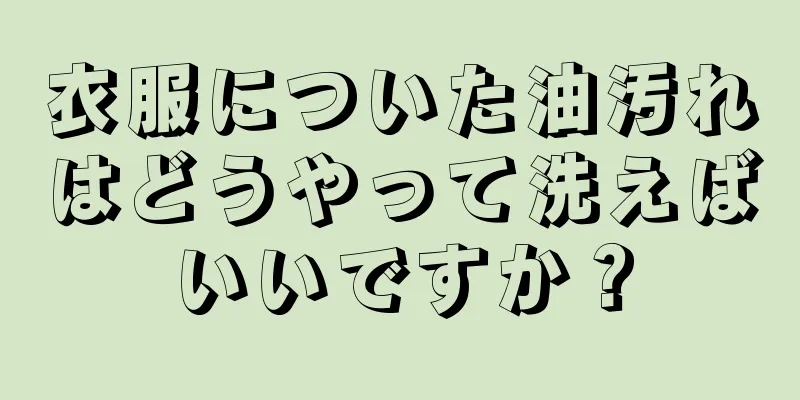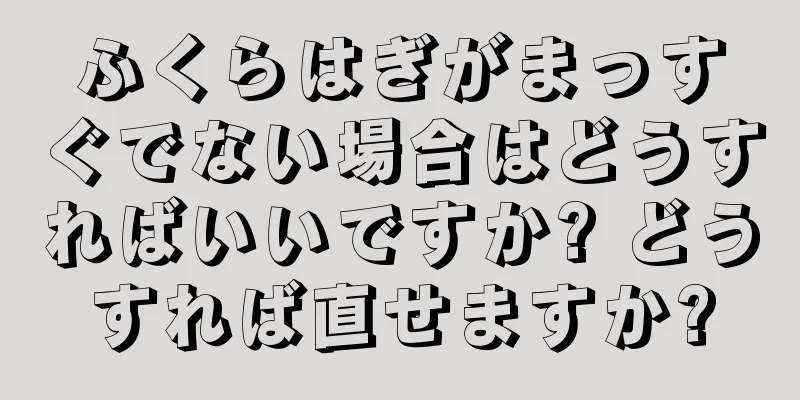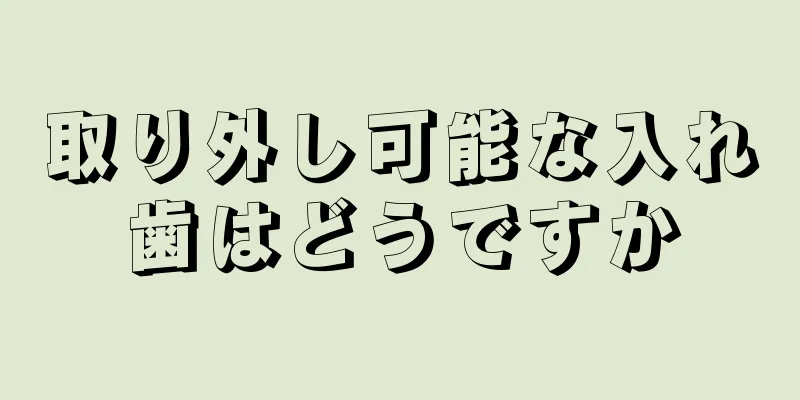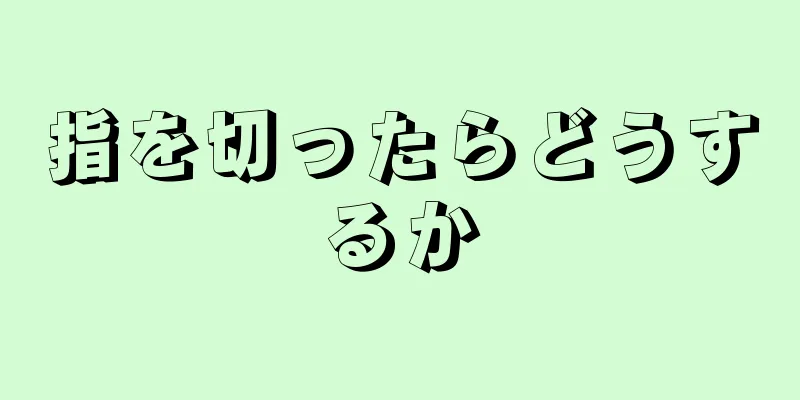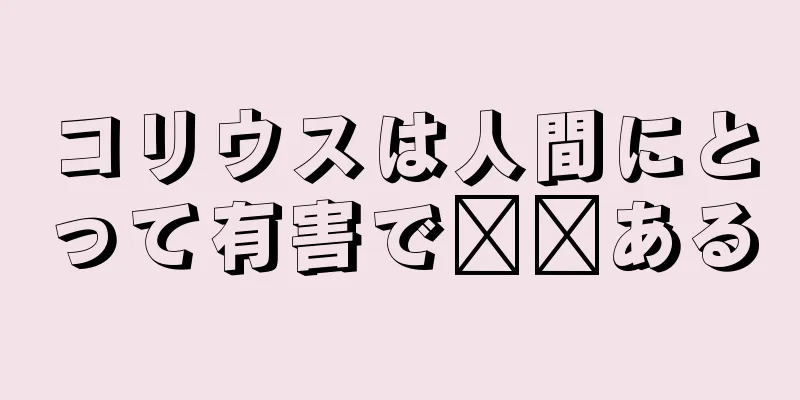腰椎椎間板ヘルニアは鍼治療と漢方薬で治療すると良い効果がある
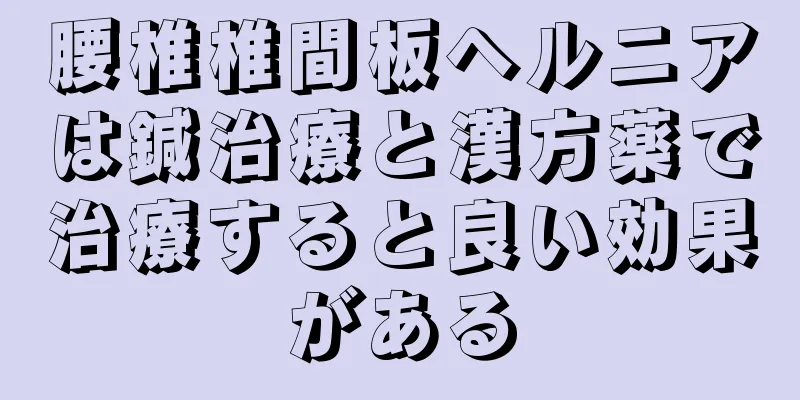
|
腰痛や脚の痛みの最も一般的な原因は腰椎椎間板ヘルニアで、特に中高年に多く見られます。この病気を治療する最良の方法は漢方針ナイフ療法ですが、鍼治療、マッサージ、牽引と組み合わせて、できるだけ早く回復させることもできます。 1. 鍼治療 緊張した筋肉やけいれんした靭帯を緩めることにより、脊椎の機械的関係が回復し、椎間板へのせん断力が軽減され、神経根の刺激や圧迫症状が緩和されます。伝統的な中国医学では、腰椎椎間板ヘルニアの痛みと痛みの放散ポイントは、下肢の甲集経と足太陽膀胱経、足陽明胃経、足少陽胆嚢経、足少陰腎経と密接に関係しています。したがって、臨床診療では、病変の位置は、治療のために伝統的な漢方薬の子午線と組み合わせる必要があります。ゾーポン、ズヒビアン、足上膀胱子午線 +フアンティアン、ヤングリン派、ヤングリン派のXuanzhong shaoyang meridian + Zusanli of the Foot yangming Meridian: Chengshan、Foot The Foot Taiyang Bladder MeridianのKunlun。さらに、ASHIポイントも鍼治療の固定点の重要な参照です。 2. 局所遮断療法 局所遮断療法には、経穴遮断と局所領域遮断の 2 種類があります。ツボブロック:鍼灸と薬物療法の総合的な治療効果があり、単純な鍼灸や単純な物質治療よりも明らかな鎮痛効果があります。よく使われる閉鎖性経穴には、三焦與、神與、大则與、指宿、足三里、環頂、衛中、成山などの経穴があります。 (1)2%塩酸リュープロレリン注射液4mlに酢酸プレドニゾロン1mlを加えてよく混ぜ、5~7日に1回、上記経穴3~4箇所に注射する。 3~5回で1回の治療コースとなります。 (2)ビタミンB12注射剤1~3mlを上記の経穴3~4箇所に注射する。 1日1回閉店となります。 1回の治療は10回です。 3. 処方薬の外用 臨床的には鍼灸、マッサージ、理学療法、腰椎牽引など多くの保存的治療法がありますが、いずれも効果が乏しかったり治療期間が長かったりする欠点があり、従来のマッサージ治療には適さず、臨床的に治療することが困難です。近年、治療効果をさらに高め、治療期間を短縮するために、自家製の漢方薬ビトンパウダーを関連するツボに塗布して急性中心性腰椎椎間板ヘルニアを治療し、一定の成果を上げている人もいます。治療方法:芍薬散(牡丹皮、芍薬、山椒、芍薬、茯苓、嘴楊花などの漢方薬成分を配合)の外用。一定の割合で粉末状に挽き、水と蜂蜜と混ぜてペースト状にし、1回につき1つのツボに約5〜10gを塗ります。ツボ処方:足ツボ、耀陽関、大昌址、観元址、耀岩、楊陵泉、環張など、病状に応じて追加または削除できます。毎回 6 ~ 7 時間外用します。患者の皮膚の炎症がひどい場合は、塗布時間を 1 日おきに 1 回に短縮できます。7 回で 1 回の治療コースとなります。 |
>>: 腰椎不安定症にはどのような対処法がありますか?保存的治療が最も一般的です
推薦する
フロストケースとソフトシリコンのどちらが良いでしょうか?
最近の人々はスマートフォンを使用しています。従来のフィーチャーフォンと比較すると、スマートフォンの利...
卵の殻を使った衣類の洗濯方法
卵の殻は私たちの日常生活で幅広い役割を果たしています。胃の不調を治療し、一定のカルシウム補給効果を達...
Amazon で模倣販売者を捕まえる 15 の一般的な方法
フォローセリングの一般的な形態小規模販売者が模倣者を捕まえるための15の一般的な方法 1. 最良の方...
独立したウェブサイト販売者にとって必読です! 2022年のShopifyに関する6つの重要な統計
権威ある組織がこのほど、Shopifyの2021年の加盟店数と売上統計を発表し、Shopifyの発展...
女王の死後ストライキは中断 エネルギー危機の中、このビジネスチャンスが生まれた!
▶国境を越えたナビゲーションをフォローするビデオアカウント英国のエリザベス2世女王が現地時間9月8...
産後疾患の治療に最適な時期
もちろん、産後疾患の治療は早ければ早いほど良いです。出産後に産後疾患の症状などの何らかの症状が現れた...
糖代謝の主な経路
人体はエネルギーを得るために糖分を必要とします。体が弱っているとき、めまいがするとき、キャンディーを...
五香粉の害
五香粉は四川料理において非常に重要な調味料です。多くのスパイスを混ぜて作られ、すべてのスパイスの真髄...
排尿回数が減ると腎不全になるのでしょうか?
腎臓は排便機能と密接な関係があります。排尿異常の多くは腎機能に関係しています。例えば、排尿回数が少な...
腹部腫瘍の症状は何ですか?
腫瘍は病気の初期段階でよく見られる病気です。病気の初期段階では、腹部の腫瘍により、患者は鈍い腹痛、下...
体の湿気に効く薬は何ですか?
体内に余分な湿気があるという考えは、伝統的な中国医学の観点から生まれました。体が湿気すぎるとリウマチ...
ブドウを長期保存する方法
ブドウは大人も子供も大好きな果物で、味もとても美味しく、気血を補い、排尿を促進し、胃を温め、脾臓を強...
体内の熱を下げ、解毒する効果のある食べ物は何ですか?
怒りは、日常生活で最も経験する可能性が高い症状の 1 つです。これは、体内に大量の毒素が蓄積されてい...
唾液が粘り気を帯びる
唾液が粘つくのは、たいてい口の渇きが原因ですが、胃の病気が原因の場合もあります。病院に行って検査を受...
神経症と精神病の違いは何ですか?
多くの人にとって、神経症と精神疾患の間に違いはないようですが、神経症は精神疾患です。しかし、この 2...