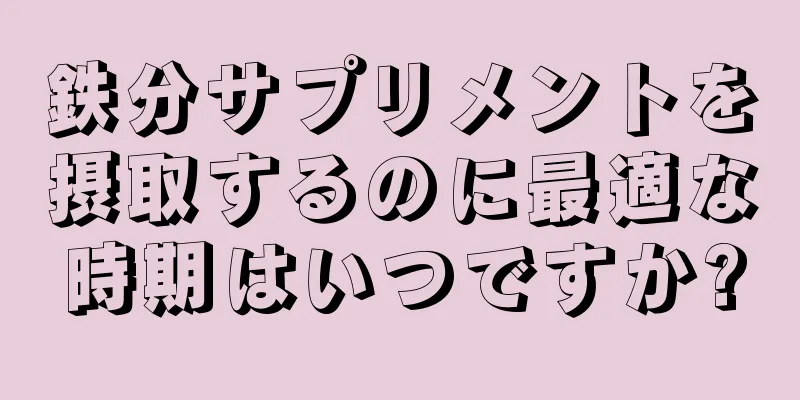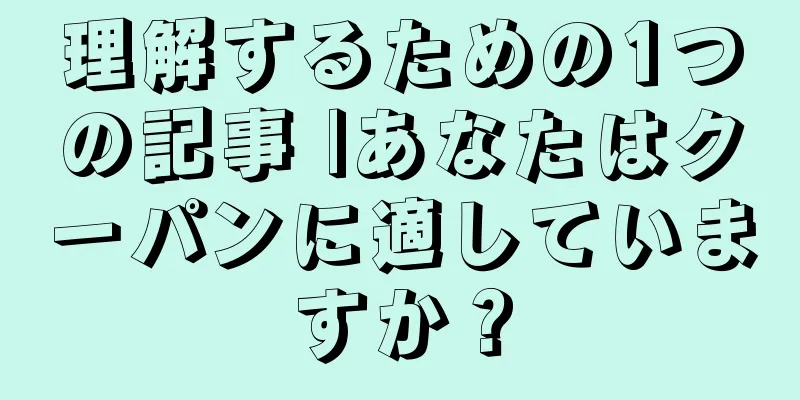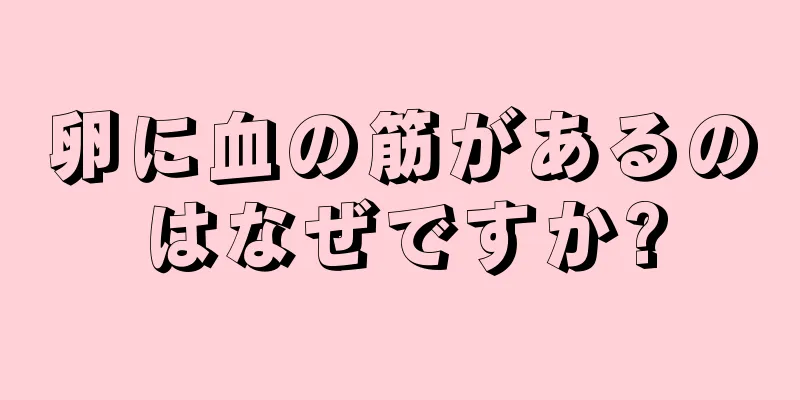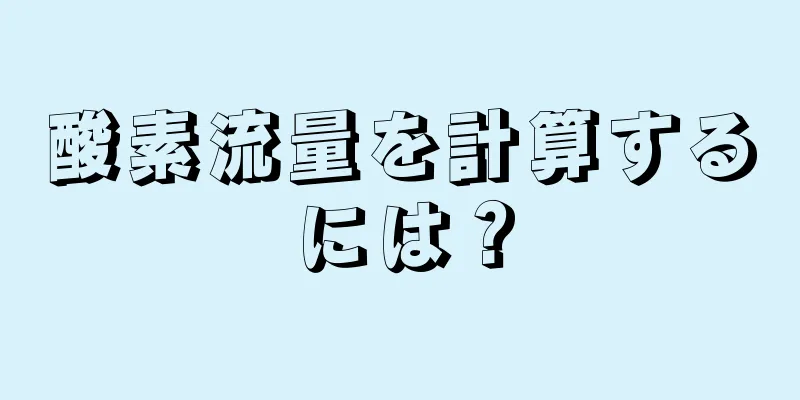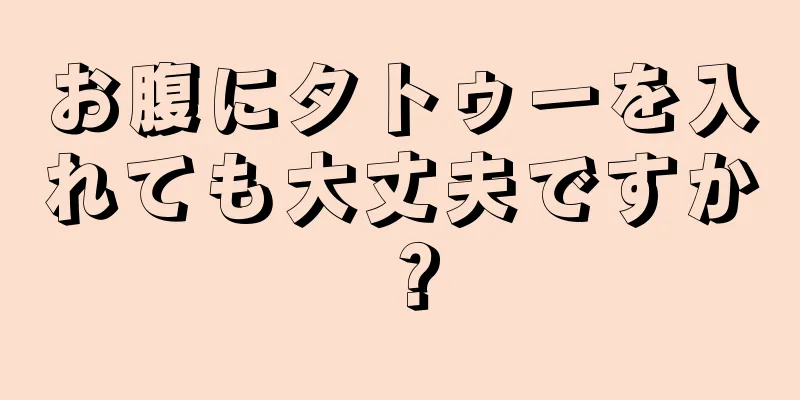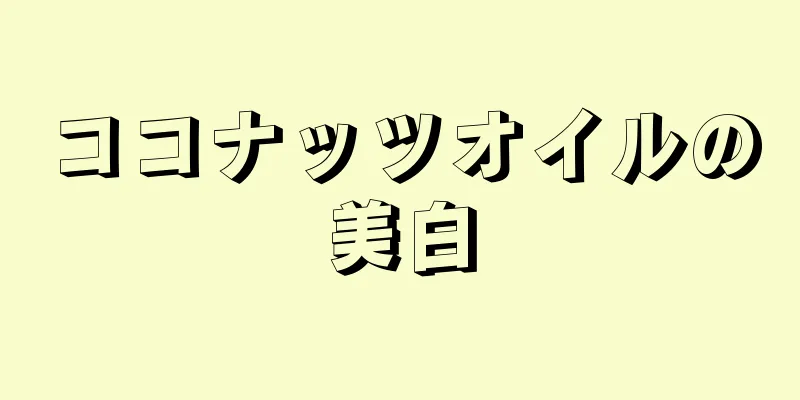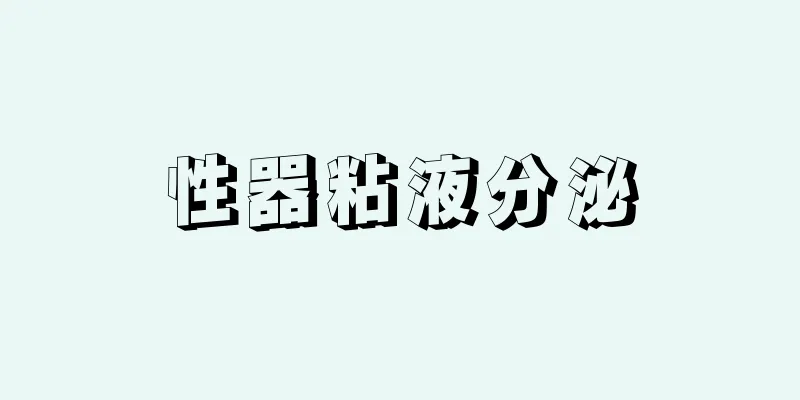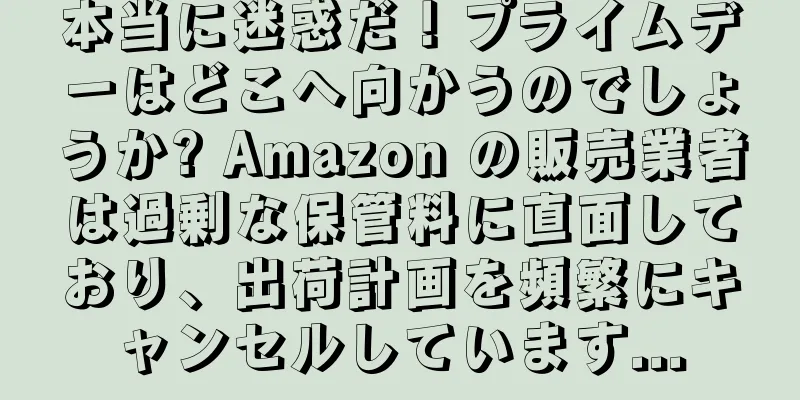動脈穿刺の手順は何ですか?
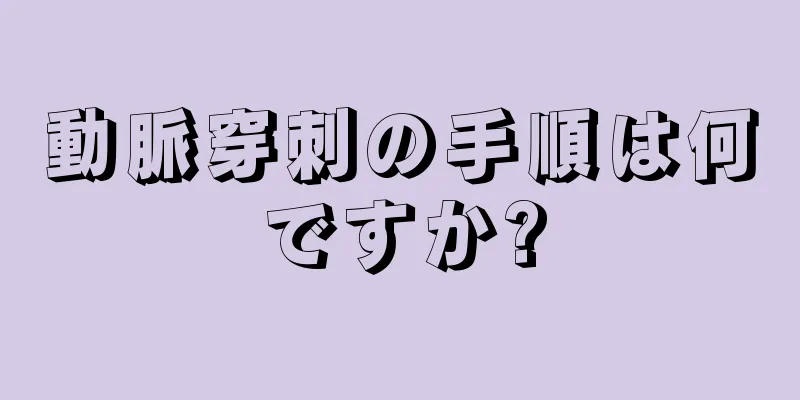
|
動脈穿刺で最も重要なことは、まず穿刺経路を見つけることです。穿刺するときは、最も明らかな動脈を選択する必要があります。針を抜いた後、血液が漏れないように医療用ガーゼまたは綿球で針穴を押さえます。腕を60度曲げると、動脈が最も明白になり、穿刺しやすくなります。 1. 穿刺経路 (1)橈骨動脈:患者の手首をまっすぐに伸ばし、手のひらを上に向け、手をリラックスさせます。穿刺点は手のひらの横線から1~2cm上の動脈脈にあります。 (2)上腕動脈:患者の上肢をまっすぐに伸ばし、手のひらを上に向けて軽く外転させる。穿刺点は肘のしわの上の動脈の拍動部に位置する。 (3)大腿動脈:患者は仰向けに寝て、下肢をまっすぐ伸ばし、軽く外転させます。穿刺点は、鼠径靭帯の中点から1~2cm下の動脈の脈拍にあります。 2. 手順(橈骨動脈と大腿動脈の穿刺とカニューレ挿入を例に挙げる) (1)橈骨動脈穿刺およびカニューレ挿入:通常は左手を用いる。患者の手と前腕を木製の板に固定し、手首の下にガーゼのロールを置き、手首を60°背屈させた。術者の左手中指で橈骨動脈に触れ、橈骨茎状突起の近位部を見つけ、人差し指で橈骨動脈の遠位端を軽く引っ張ります。穿刺点は 2 本の指の間です (図 6-83)。通常の皮膚消毒とドレープ、および 1% プロカインまたはリドカインによる局所麻酔の後、術者は右手に針を持ち、中指で触れた橈骨動脈の方向を狙って皮膚に対して 15 度の角度で針を挿入し、動脈に近づいたときのみ動脈を穿刺します。針の先端から血液が噴出すればガイドワイヤーを挿入できます。血液が噴出しない場合は、血液が噴出するまで針をゆっくりと引き抜くと、穿刺が成功したことがわかります。ガイドワイヤーを挿入する際に抵抗があってはなりません。抵抗がある場合は挿入しないでください。挿入すると動脈を貫通し、軟部組織に入り込んでしまいます。最後に、ガイドワイヤを通してプラスチックカテーテル(図6-84)を挿入し、カテーテルを固定して圧力を測定します。 (2)大腿動脈穿刺とカニューレ挿入:鼠径靭帯の中点から1~2cm下の大腿動脈脈に触れます。左手の人差し指と中指を動脈脈の表面に置き、人差し指と中指を離し、2本の指の間の穿刺点を選択します。通常の皮膚消毒、ドレープ、局所麻酔を行います。針は右手に持ち、皮膚に対して 45 度の角度で挿入します。残りは橈骨動脈穿刺およびカテーテル挿入と同じです (図 6-85)。 3. 注記 1. 動脈穿刺は、動脈血採取と動脈ショック注入療法が必要な場合にのみ使用されます。 2. 穿刺点は動脈の脈動が最も顕著な場所を選択する必要があります。 3. 針を抜いた後、ガーゼや綿球を使って圧迫し、出血を止めます。圧迫後も出血が続く場合は、血腫の形成を防ぐために、出血が完全に止まるまで圧迫包帯を巻いてください。 4. カテーテル関連感染を防ぐため、カテーテル挿入時間は 4 日を超えないようにしてください。 5. 留置カテーテルは、パイプラインの開存性を確保し、局所血栓症や末梢塞栓症を回避するために、ヘパリン溶液(速度 3 ml/h、ヘパリン濃度 2 u/ml)で継続的にフラッシュする必要があります。 |
推薦する
リンパ腫を調べるには?リンパ腫の診断方法
リンパ腫といえば、局所的な病理学的疾患です。現在の臨床では、各疾患の変化は異なります。多発性のものも...
崑崙雪菊はどんな人に適していますか?
崑崙雪菊には優れた健康効果があります。例えば、高血圧の人が毎日崑崙雪菊を4グラムほど、つまり朝に2グ...
脳梗塞にステントは使えますか?
脳梗塞は多くの人の健康を危険にさらします。脳梗塞が発生すると、患者は失神するため、積極的に治療する必...
無酸素運動心拍数
日常生活では、無酸素運動を特に好む人が多いです。有酸素運動に比べて、無酸素運動は運動量が少なく、体が...
肝機能検査を受けるには絶食する必要がありますか?
面接に合格した後、会社から肝機能検査を受けるよう求められる友人は多いと思います。B型肝炎の発生により...
誤ってデーツの種を飲み込んだ場合のヒント
ナツメは私たちの生活の中で一般的な食べ物です。ほとんどの人がナツメを食べるのが好きです。ナツメは栄養...
アレルギーや赤みがある場合の対処法
多くの人は、生活の中でアレルギーや赤み、腫れに悩まされています。これらはすべて皮膚の問題です。日常生...
心臓超音波検査では何が検出できますか?
心臓は人体で最も重要な臓器です。心臓に病気があると、人々の健康に大きな影響を与えます。そのため、病気...
髪の毛を飲み込んだらどうするか
私たちの生活の中で、髪の毛を誤って胃の中に食べてしまう人がいます。特に女性の場合、髪の毛が比較的長く...
いくら食べても太らないのはなぜですか?
いくら食べても太らない体質を持って生まれてくる人もいます。肉や魚を食べ過ぎても、ほとんど太りません。...
精巣上体結節の大きさはどれくらいですか?
精巣上体硬結は精巣上体によく見られる健康問題です。この問題は精巣上体炎と密接に関係しています。精巣上...
リス肉の効能と食べ方は何ですか?
松は一般的な野生動物で、普通のネズミよりも大きく、ペットとして飼育することができ、非常に経済的です。...
スチームクリーナー300万台以上が緊急リコール! Amazonやその他のプラットフォームで入手可能
米国消費者製品安全委員会(CPSC)が最近、火傷の危険性を理由に、BISSELLのSteam Sho...
足を紅花に浸して減量する場合の注意点は何ですか?
足湯は、冬に多くの人が好むアクティビティです。一般的に、睡眠を促進し、疲労を解消する効果があると考え...
風邪で鼻が詰まったらどうすればいい?解決に役立つ4つのヒント
風邪はあらゆる年齢層の人に起こりうる非常に一般的な病気であり、風邪の主な症状の 1 つは鼻づまりです...