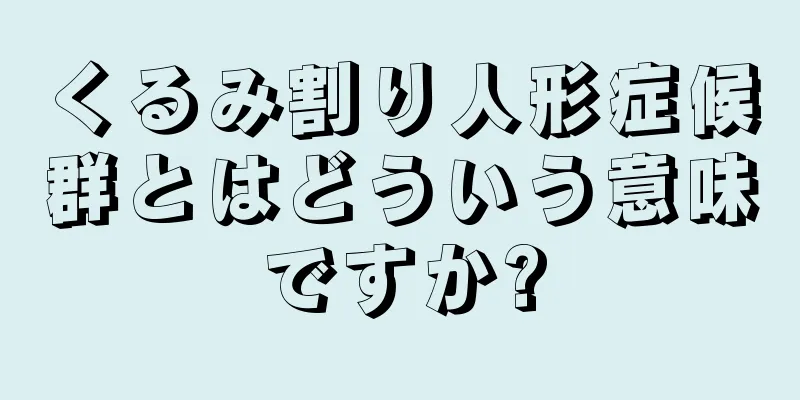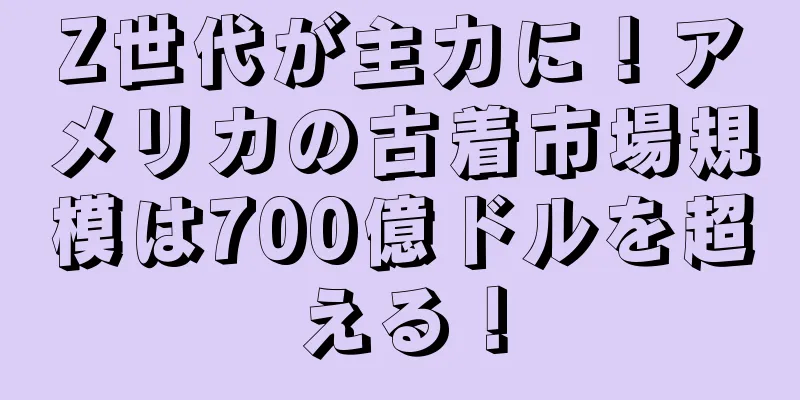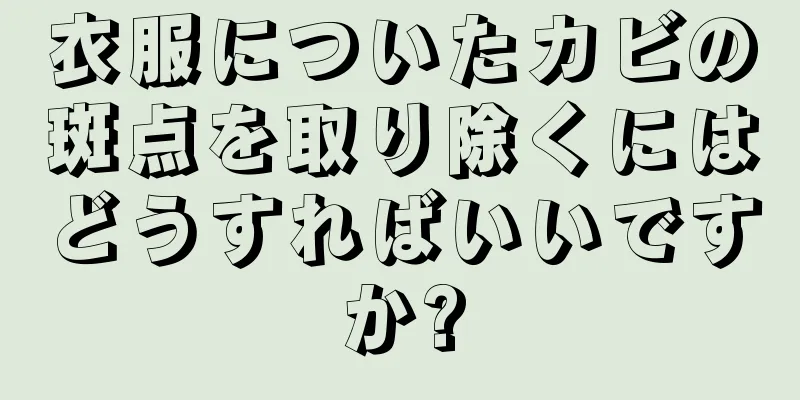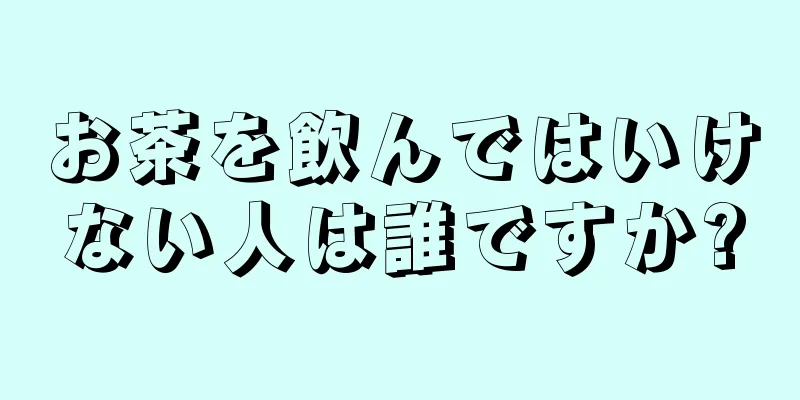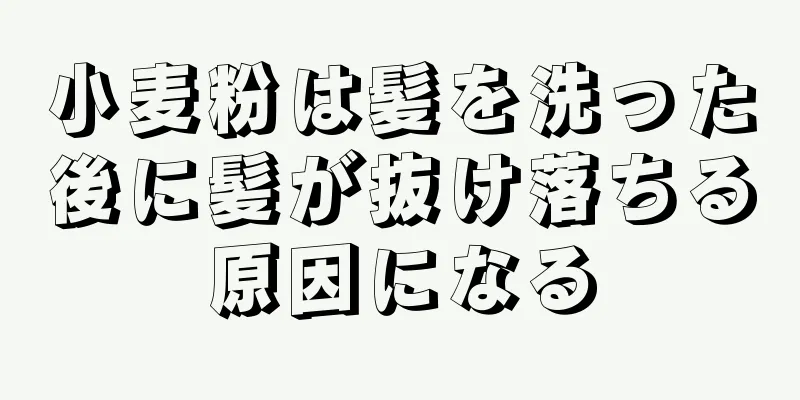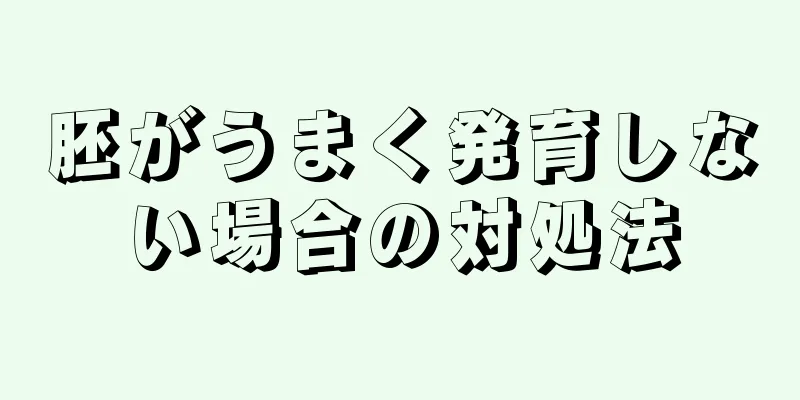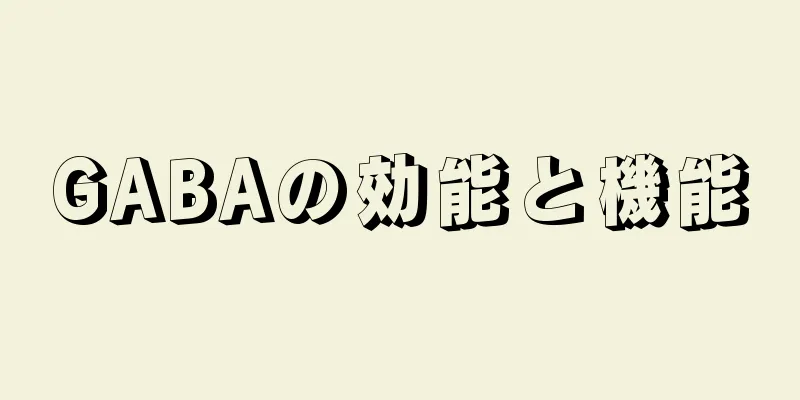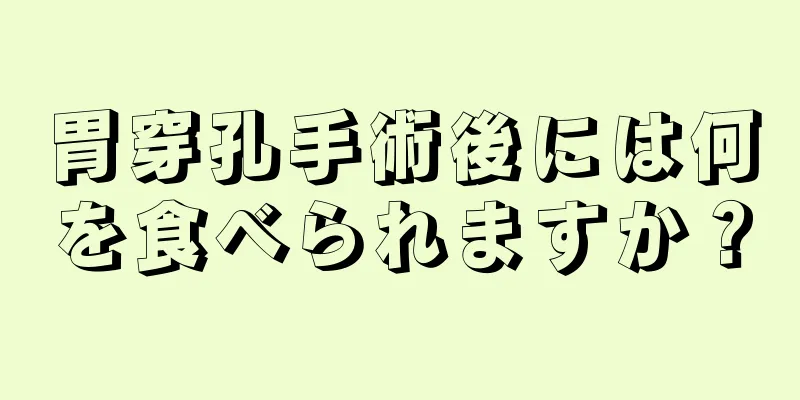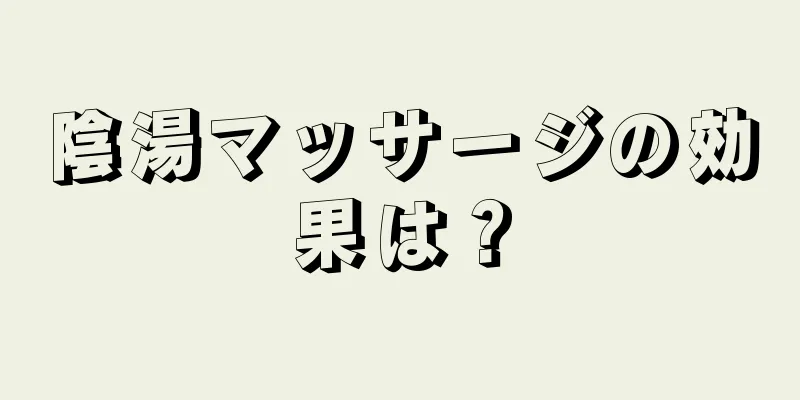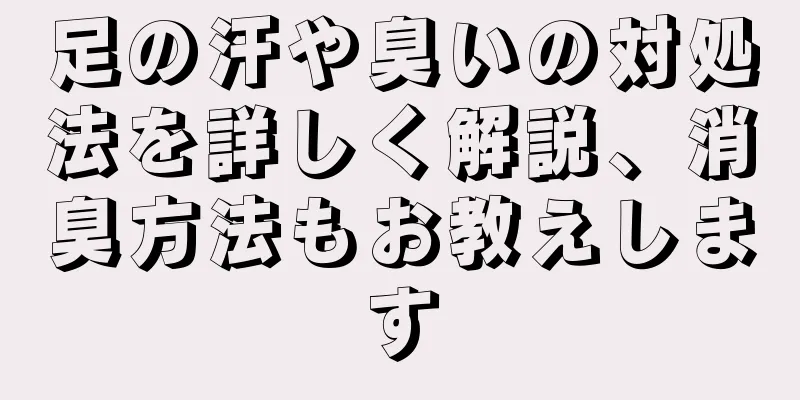L-カルニチンは授乳中に摂取できますか?
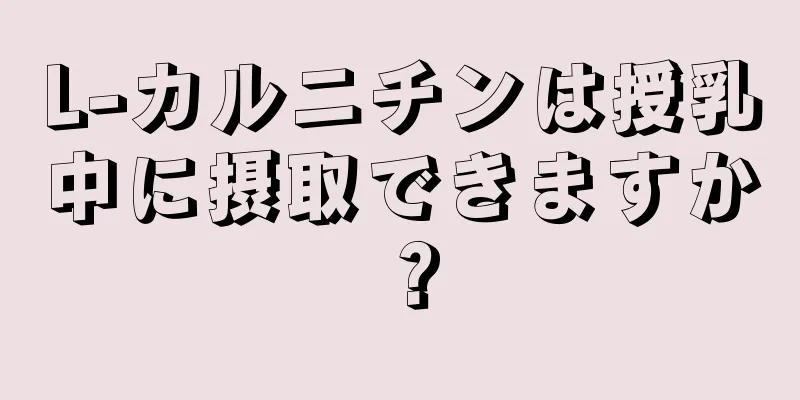
|
妊娠10ヶ月は妊婦の体型に大きな影響を与えます。授乳期に入ると、多くの女性の体は基本的に変形します。しかし、妊娠中に比べると授乳中の状況ははるかに良く、授乳中は減量にとても良い時期だと言われています。そのため、多くの女性は短期間で体重を減らすという目標を達成するためにダイエット薬を使用したいと考えています。では、授乳中にL-カルニチンを摂取してもよいのでしょうか?以下で見てみましょう。 この場合は服用しないことをお勧めします。 授乳中に早く体重を減らす方法 実は産後の減量にはゴールデンタイムというものがあり、そのゴールデンタイムに合わせて段階的に進めていけばいいので、授乳中の減量はより効果的です。授乳中の減量に最適な時期を見てみましょう。 1. 出産後1ヶ月以内に体重を減らさないでください。一般的に、出産後1ヶ月は母親が回復する期間です。産後期間中の女性の採用は、彼女たちの身体の健康にとって非常に重要な役割を果たし、産後の回復にとって重要な期間です。一般的に、出産後1か月間はすぐに体重を減らさないことが推奨されます。ただし、産後の回復が順調であれば、お母さん自身の回復状況に合わせて、腹筋運動などの簡単な運動をすることができます。 2. ご自身の状況に合わせて、出産後6週間から減量を開始できます。運動量は自分の許容度に応じて決めてください。このとき、産後減量栄養レシピを使用して減量をサポートすることもできます。 3. 出産後2ヶ月で適度に体重を減らすことができます。産後2ヶ月で産後うつ期間は一般的に終了し、適度に体重を減らすことができます。 4. 出産後 4 か月で減量の努力を強化できます。出産後4か月で、体は基本的に出産前のレベルまで回復します。このとき、運動量は適切に増やすことができますが、食事と栄養は依然として維持する必要があります。 5. 出産後の最初の 6 か月は減量にとって重要な期間です。忍耐こそが究極の勝利です。減量後のリバウンドを防ぐために、簡単なエクササイズと退屈な食事療法を続けましょう。 |
推薦する
慢性大腸炎の症状は何ですか?
慢性大腸炎と直腸炎は比較的よく見られる病気です。患者がこの病気にかかると、症状もより顕著になり、特に...
装飾の匂いにアレルギーがある場合の対処法
多くの人は新しい家を購入した後、それを装飾しますが、装飾の匂いは比較的強く、特にホルムアルデヒドの匂...
ピーナッツの赤い皮は食べられますか?
ピーナッツをどのように食べるかに関係なく、多くの人はピーナッツの皮の外側の層を剥く習慣があります。こ...
圧縮袋の使い方
圧縮袋は真空圧縮袋とも呼ばれ、実は私たちの身の回りで広く使われていますが、私たちが普段目にする圧縮袋...
リウマチ性心疾患による僧帽弁狭窄症の最も一般的な合併症は何ですか?
リウマチ性心疾患は主に僧帽弁閉鎖不全症または狭窄症によって引き起こされます。リウマチ性心疾患が早期に...
鹿の角はどんな人に向いているのでしょうか?
鹿の角は非常に高価な栄養食品で、特に体に有益な多くの物質が豊富に含まれています。鹿の角をたくさん食べ...
赤ちゃんは生まれてからどれくらい早く予防接種を受けるべきですか?
子供がかかりやすい多くの病気、特に一部のウイルス感染症の場合、最善の方法は予防接種を受けることです。...
上まぶたが重くなる原因は何ですか?
多くの人は、生活の中で目に何らかの変化があり、それが通常の目とはかなり異なると感じるでしょう。たとえ...
ダウンジャケットのアヒルの羽毛の臭いを防ぐためのヒント
寒い冬は、気温も低く風も冷たいので、暖かさを保つためにダウンジャケットが必要です。ダウンジャケットに...
アルコールの臭いを取り除く方法
集まる場所に行くたびに、必然的にアルコールの臭いがします。アルコールの臭いを隠すために、服を洗ってか...
民俗スナックの作り方
数百、数千年にわたる発展を経て、中国人はさまざまな特製スナックを開発してきましたが、各地域のスナック...
血圧が下がるとめまいを感じるのはなぜですか?
高血圧は身体に大きな害を及ぼす可能性があるため、多くの患者は高血圧症に気付いた後すぐに薬を服用し始め...
なぜ夜に爪を切ってはいけないのですか?
老人たちは、夜に子供の爪を切るのは子供にとって良くないからやめなさいとよく言います。しかし、なぜ夜に...
喉と胸が冷たくて詰まった感じがします。
時には、一見深刻な病気が、実は悪い生活習慣によって引き起こされることもあります。例えば、胸が締め付け...
Amazon US の購入者にとって最大の問題点は何ですか?読めば分かる
デジタルトランスフォーメーション企業ブルックス・ベルが最近、アマゾンで買い物をする際にアメリカの消費...