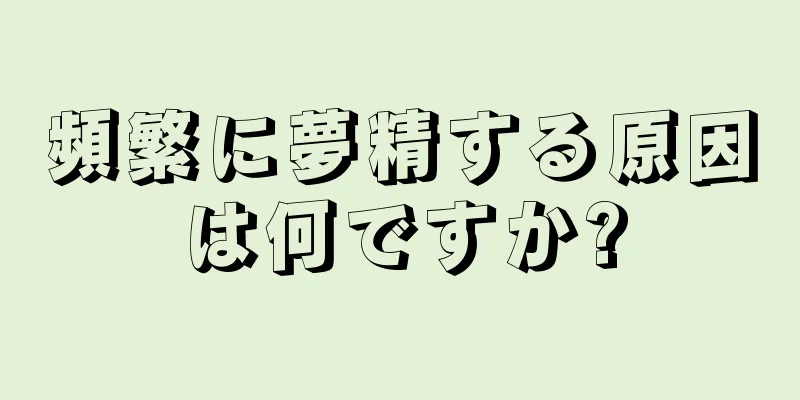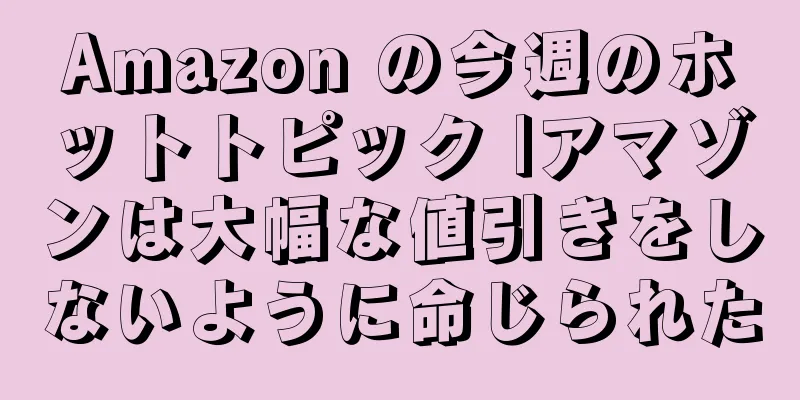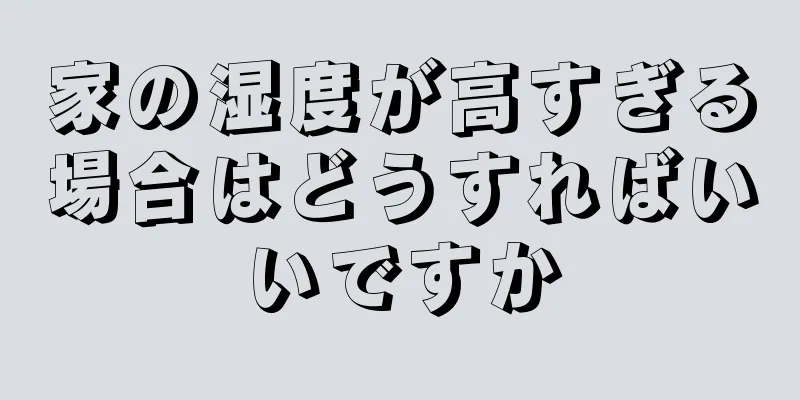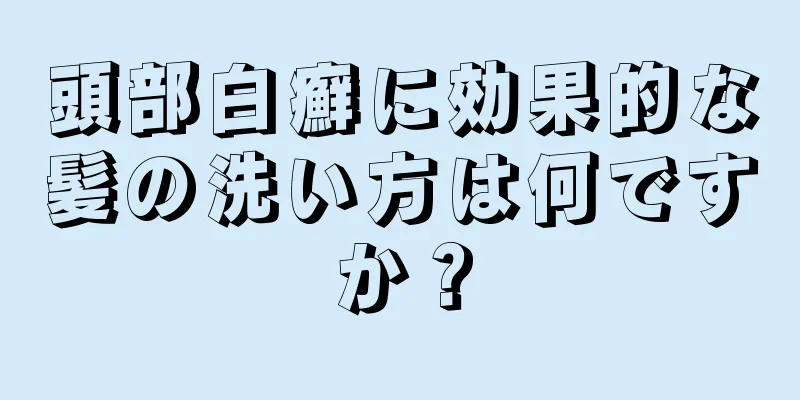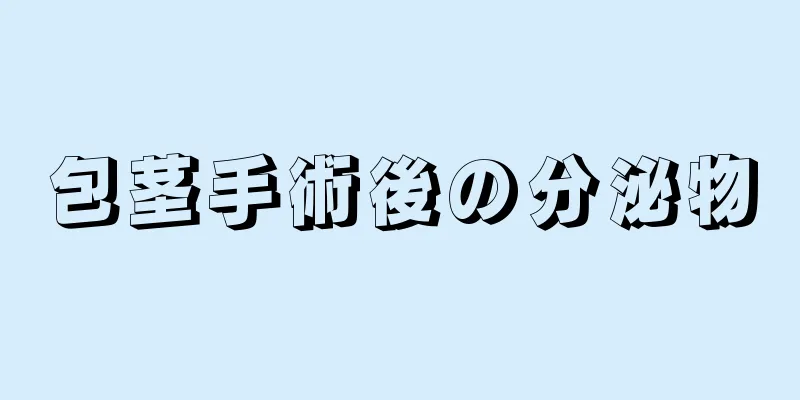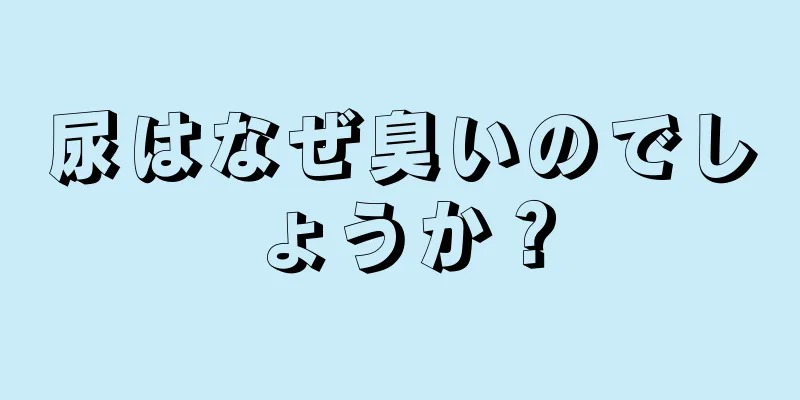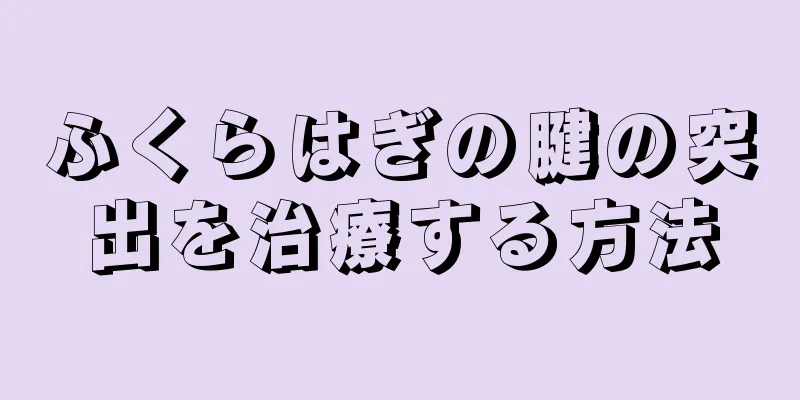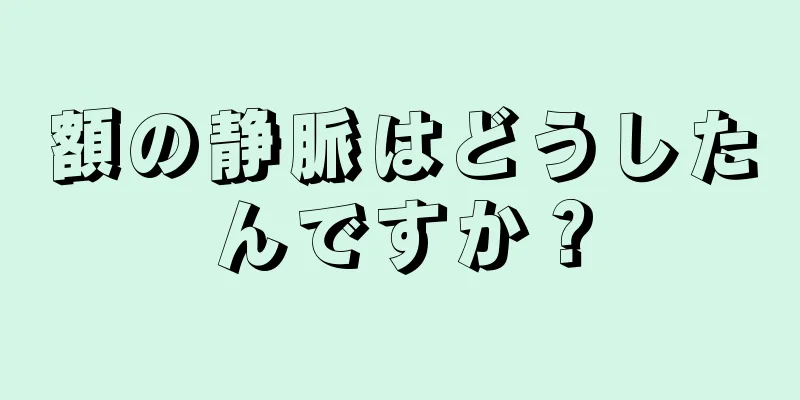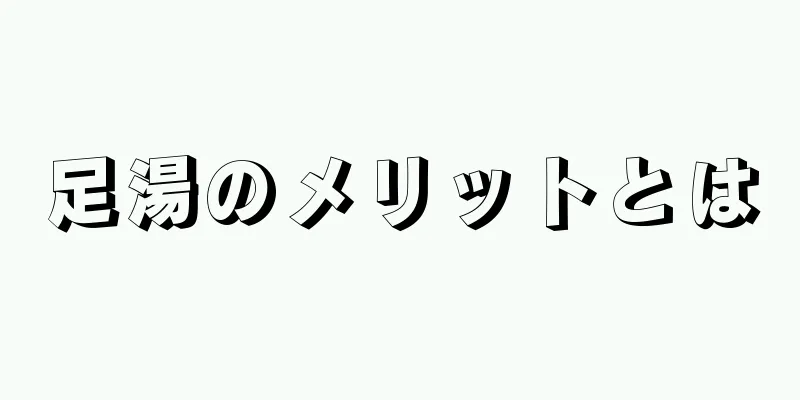血液を活性化したり、血液の停滞を取り除く薬を服用すると流産の原因になりますか?
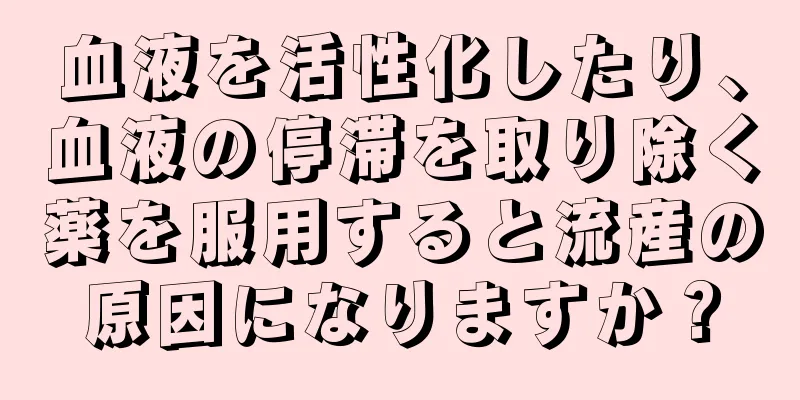
|
血液循環を促進し、瘀血を除去することができる薬は多くあり、瘀血を治療し、人体のさまざまな症状を緩和および治癒することができます。ただし、妊婦など、すべての人が血液活性薬や血液瘀血除去薬の服用に適しているわけではありません。これは妊婦の場合流産を引き起こす可能性があるため、妊婦と胎児の安全にとって非常に危険です。次に、活血薬と瘀血薬に関する知識を紹介します。 1. 血液うっ滞の症状 一般的に、血液うっ滞は冠状動脈疾患を患う高齢者によく見られます。このグループの人々の典型的な症状は、息切れ、胸痛、その他の不快感を伴うことが多く、体のどこかに針で刺されたような痛みがあり、夜間に痛みがひどくなり、顔色がくすんで生気がなくなり、目の下にクマができやすくなります。中国中医学院西園病院の楊立教授は、瘀血の原因は3つあると述べています。 1. 傷のない外傷は、局所的な打撲、腫れ、痛みのみを引き起こします。 2. 血液循環が悪い、または弱い。 3. 寒さや暑さの影響で血液の停滞が起こります。 2. 血液を活性化し、うっ血を除去する薬 血管を清め、血流を促進し、瘀血を解消する働きを持つ薬は、活血薬、瘀血除去薬と呼ばれ、活血薬とも呼ばれます。血液を活性させる薬物を用いて血液循環障害や体内の血液の停滞を治療する方法を活血法といいます。活血薬は、主に辛味、苦味、塩味があり、性質は冷、温、中性です。主に肝経と心経に属し、胸部と脇腹の痛み、リウマチの痛み、傷跡やしこり、傷による腫れや痛み、打撲や痛み、また瘀血による月経不順、無月経、月経困難症、産後の腹痛などの治療に用いられます。 薬効の異なる特徴によって、滋血・活血薬(タンジン、当帰、ボタンなど)、活血・瘀血除去薬(川芎、ベニバナ、花粉菌など)、瘀血除去・鎮痛薬(乳香、没薬、エンゴサクなど)、破血・解結薬(エンレイソウ、ガジュツ、モクレンなど)に分けられます。 活血・除血薬は、血液の停滞を除去して新血を促進し、血管を拡張し、血液循環を促進し、血流を増加させて、心血管疾患や脳血管疾患、婦人科疾患、外傷性疾患などの血行不良の疾患を治療するだけでなく、血液循環を活性化して内臓の機能を調整し、新陳代謝を促進し、自身の病気に対する抵抗力を高め、老化を遅らせる効果もあります。 3. 血行促進と瘀血除去の注意点 1. 活血薬と瘀血除去薬は、さまざまな瘀血疾患に適していますが、それぞれに長所と短所があり、具体的な症状に応じて適切に選択する必要があります。 2. 瘀血は気血循環不良の原因となることが多いため、血行促進や瘀血除去の効果を高めるために、気調整薬と併用されることが多いです。瘀血や潰瘍がある場合は清熱薬と併用します。 3. 活血薬や瘀血除去薬は血液を損傷するリスクがある場合が多いので、使用時には用量に注意する必要があり、必要に応じて滋養強壮薬と併用することをお勧めします。 4. 瘀血や気虚の方には、補気薬と併用してご使用いただけます。 5. 月経過多の女性や妊娠中の女性は、血液活性薬や血液瘀血除去薬の使用を避けるか、慎重に使用する必要があります。 |
<<: 炎症を抑え、血液循環を活性化し、血液の停滞を取り除くために使用される薬は何ですか?
推薦する
ライブストリーミング販売は海外でも人気ですが、国境を越えたライブストリーミングは次の富を生み出すトレンドになるのでしょうか?
国内メディアの報道によると、電子商取引ライブ放送サービスプラットフォームWahoolは最近、2回連続...
タンパク尿とは何ですか?
タンパク尿とは何ですか? 尿タンパクと診断された後、多くの友人がこの質問をするでしょう。いわゆる尿タ...
衣服についた油汚れを落とす方法
冬が来て、半袖やショートパンツなどの夏服を脱いで、セーターやコートを着る季節になってきました。暖かく...
歩くと足の裏が痛くなるのはなぜですか?
足は人体を支える四肢の1つです。足が耐えられる圧力は非常に大きく、全身の重量のほとんどが足で支えられ...
甲状腺機能亢進症の症状は何ですか?
甲状腺機能亢進症は、20 歳から 40 歳の人によく見られる病気で、男性よりも女性に多く見られます。...
粗塩の精製手順
粗塩という言葉は皆さんも聞いたことがあると思います。これは海水や塩井などの塩水から採取した塩の一種で...
人体の中で最も脆弱で致命的な部分
人体には「転倒」に非常に強い部位もあれば、非常に壊れやすく、スポーツや事故の際に簡単に怪我をし、命を...
鼻血を止める方法
鼻血は鼻血で、よくある病気です。鼻血の原因は生理的なものと病気的なものの両方を含めて、いろいろありま...
五穀豆乳の合わせ方
人々の生活水準が向上するにつれて、人々は食生活における健康とウェルネスにますます注意を払うようになり...
顎の近くの白癬にはどんな薬を使えばいいですか
顎に異常が起きることは一般的にありませんが、人によっては顎に白癬が発生することがあります。このような...
肺を侵す風寒の症状
風邪による肺炎の症状に気づかない人も多いので、早めに治療する必要があります。風や寒さによって引き起こ...
皮膚疾患の原因
皮膚疾患は比較的広い概念であり、最も一般的な疾患の1つです。さまざまな症状と発現が含まれます。皮膚疾...
小さな血の混じった痰
時々、痰を吐くときに血が混じることがあります。このような状況に遭遇すると、何が原因なのかわかりません...
ヘアカラーは有毒ですか?
髪を染めることは、現代人のファッションと美の追求の象徴となっています。見た目を良くするため、また髪本...
アメリカでは「男性美容経済」が台頭している。この軌道に賭けている小売業者はいくつありますか?
最新の Digital Commerce 360 分析によると、男性用グルーミング市場は活況を呈...