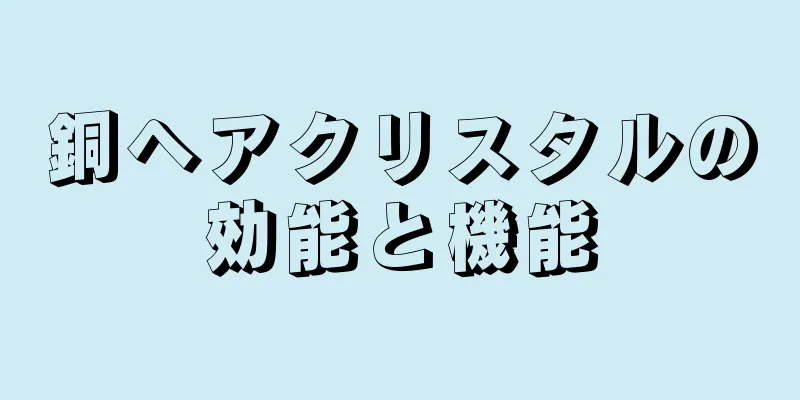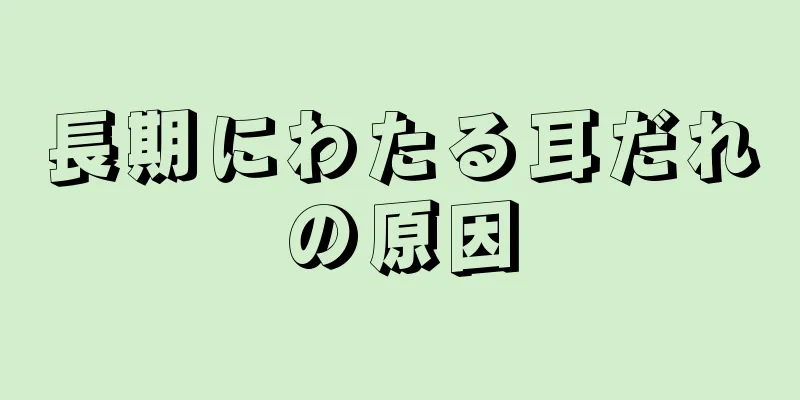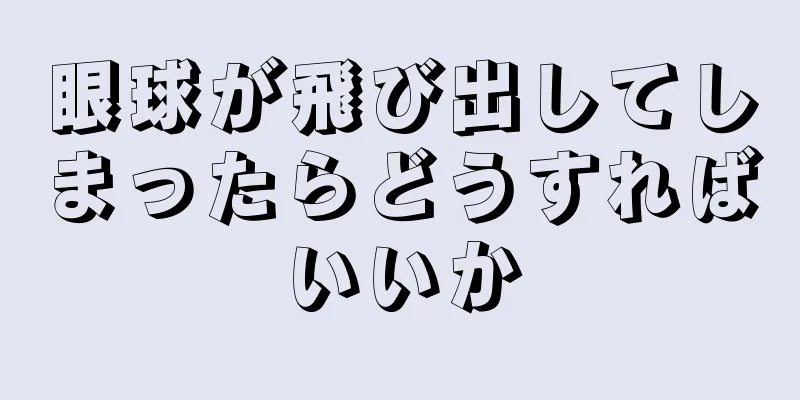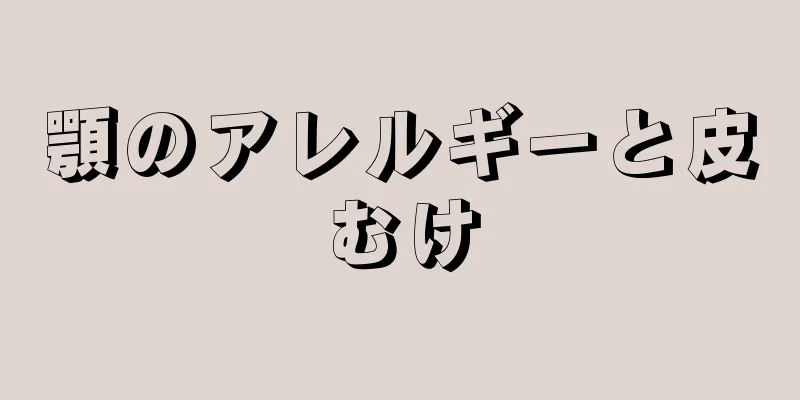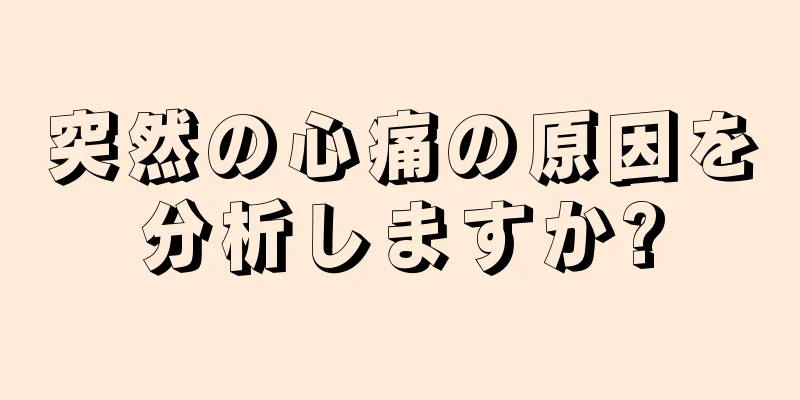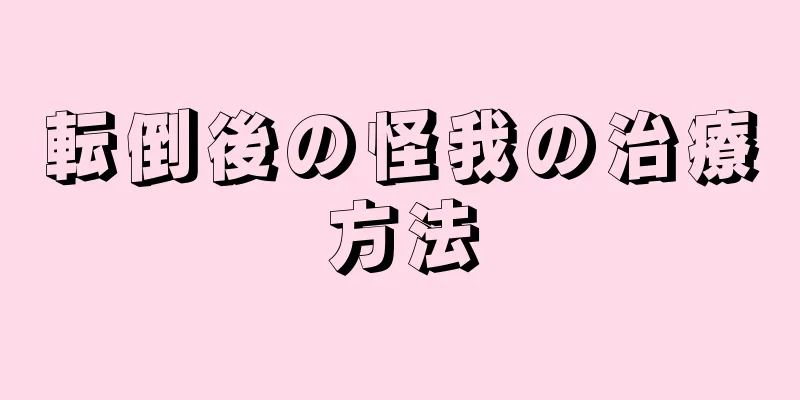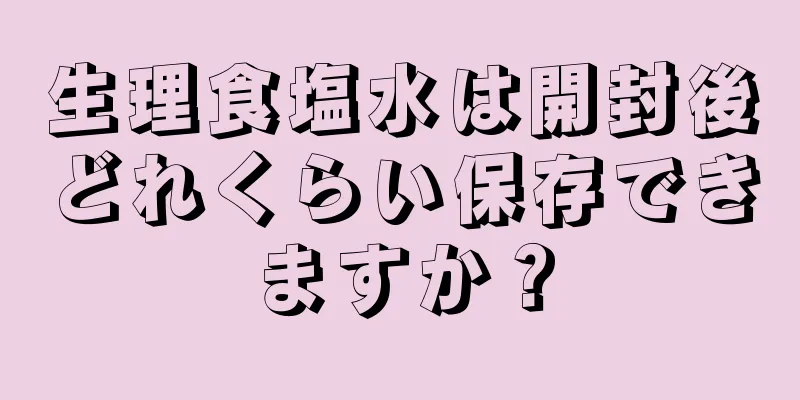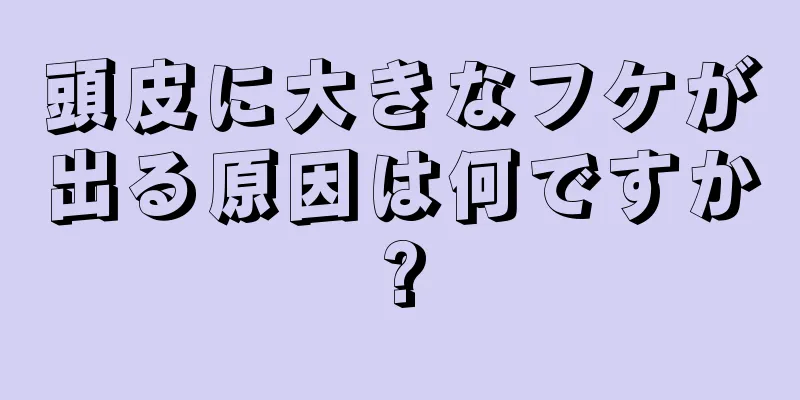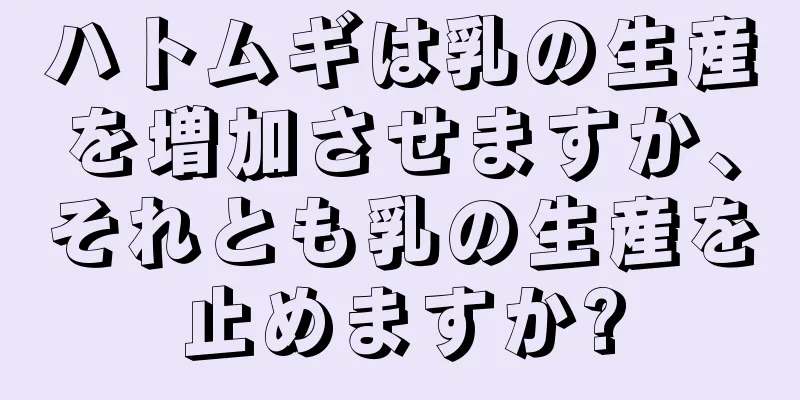長期にわたる片側の鼻づまり
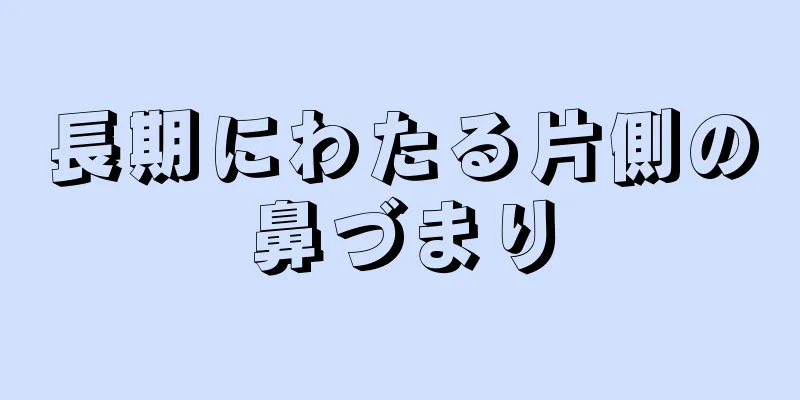
|
鼻づまりは非常に厄介な問題です。長期間続くと、人々の健康に一定の影響を与えるだけでなく、人々の精神状態にも一定の影響を与えるからです。そのため、鼻づまりが起こった後は、早急な治療が必要となります。では、鼻づまりの症状を効果的に緩和するにはどのような方法があるのでしょうか?ここにいくつかのヒントがあります! 1. 辛い食べ物を食べる 辛い食べ物は鼻の粘膜液を浄化し、鼻づまりを和らげるのに役立つため、一時的な鼻づまりであれば、辛い食べ物を食べることですぐに鼻づまりを和らげることができます。 2. 顔に温湿布 タオルを温水に浸し、絞って乾かし、数分間顔をタオルで覆います。これにより、鼻腔がきれいになり、鼻づまりが緩和されます。または、熱いお湯の上に顔を置き、熱い蒸気が肺と鼻腔に入るようにすると、鼻腔内の粘液が排出され、鼻づまりが効果的に緩和されます。 3. 足をお湯に浸す 鼻づまりのときは、足をお湯に浸すのも効果的です。寝る前に足を浸すと、足裏のツボに熱が伝わり、血行が促進され、鼻づまりを効果的に緩和できます。 4. 拳で脇の下を押す 脇の下には自律神経の圧感知機構があるため、この機構が圧迫されると、体の交感神経が刺激され、血管が収縮して、鼻腔の詰まりが解消されます。そのため、拳で脇の下を10秒間押すと、鼻づまりの症状がすぐに緩和されます。鼻の左側が詰まっている場合は右脇の下を押し、鼻の右側が詰まっている場合は左脇の下を押します。 5. ツボをマッサージする 人差し指を使って、鼻の両側のくぼみにあるツボをマッサージします。1回につき3秒間押し、6秒間リラックスします。1セットは9秒間です。マッサージを3回繰り返すと、鼻腔の詰まりがすぐに解消され、快適になります。 6. 薬の使用 風邪やアレルギーが原因で鼻づまりを経験する患者もいます。このとき、抗アレルギー薬を使用すると、鼻づまりの症状をすぐに緩和できます。ただし、これらの薬は医師の指導の下で使用する必要があり、特に特定の病気の人には盲目的に使用することはできないことに注意してください。 |
<<: ヒアルロン酸の塊が消えるまでにどれくらいかかりますか
推薦する
豚の腸の扱い方
生の豚腸を市場で買ったら、家に帰ってから丁寧に扱う必要があります。豚腸を何度も洗って、汚れを徹底的に...
これらの習慣が聴力を奪わないようにしてください
悪い習慣1:職業性騒音による聴覚障害は無視できない3年以上連続的に騒音にさらされた人の場合、純音聴...
尿失禁は以下のように分けられます
尿失禁の症状は主に高齢者に発生します。これは主にウイルス感染が原因です。また、膀胱破裂による排尿コン...
午後に超音波検査をするのは正確ですか?
実際、B 超音波検査には特定の時間制限はありません。いつでも実施でき、午後に実施する方が必ずしも正確...
アテロームと脂肪腫の違い、両者の見分け方を教えます
乾癬は真菌感染により起こる病気ですが、脂肪腫は良性の腫瘍です。血管腫が発生した場合は手術による切除が...
ダブル液体グラウトポンプの使い方は?
現代産業の急速な発展により、多くの先進的な機械設備が生まれ、生産が大幅に自由化され、効果も向上しまし...
足の血栓の症状
血栓症は人体のどの部位でも発生する可能性がある、非常に頑固で治癒が難しい病気です。血栓症とは、血管が...
耳がかゆい、耳垢が多すぎるのはなぜですか?
普段は外耳道の状態が正常でも、突然耳垢が増えて聴力に影響が出るようになったら、何が起きているのか注意...
ヨモギと紅花の足湯の効能と役割、健康効果
最近では、多くの人が身体の健康を重視し、足を浸す習慣があります。定期的に足を浸すと、体全体の血液循環...
大腿骨頸部骨折は完全に治癒できますか?
大腿骨頸部骨折は完治できるのでしょうか?高齢者は骨粗鬆症により骨折しやすく、大腿骨頸部骨折は高齢者に...
鼻の両側の黒ずみを除去する方法
現代の概念により、顔の状態に細心の注意を払う人が増えています。古代から現代に至るまで、美を愛すること...
先天性甲状腺機能低下症の疑い
甲状腺は人体にとって重要な組織であり、甲状腺ホルモンを分泌する臓器です。甲状腺は骨の発達や首のむくみ...
双子を妊娠するにはどうすればいいですか?
赤ちゃんを授かる準備をしているカップルのほとんどは、双子を授かることを熱望していると思います。特に、...
子どもの歯の病気の危険性は何ですか?
子どもは甘いものを食べるのが好きで、おやつにはいつもたくさんの甘いものが含まれています。これは簡単に...
衣服についた血痕を落とすには? 洗浄のヒントをいくつかご紹介します
日常生活では、何らかの理由で怪我をし、血が衣服に付くことがあります。また、怪我人を治療しているときに...