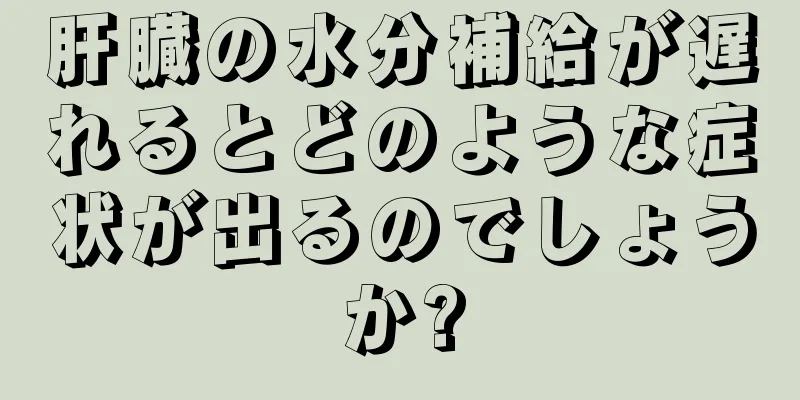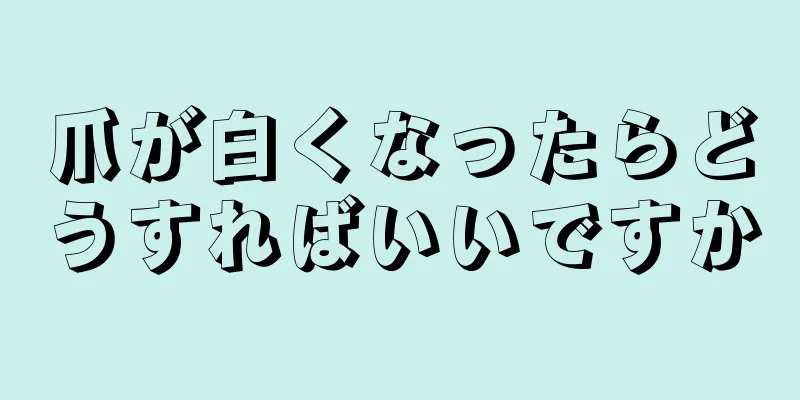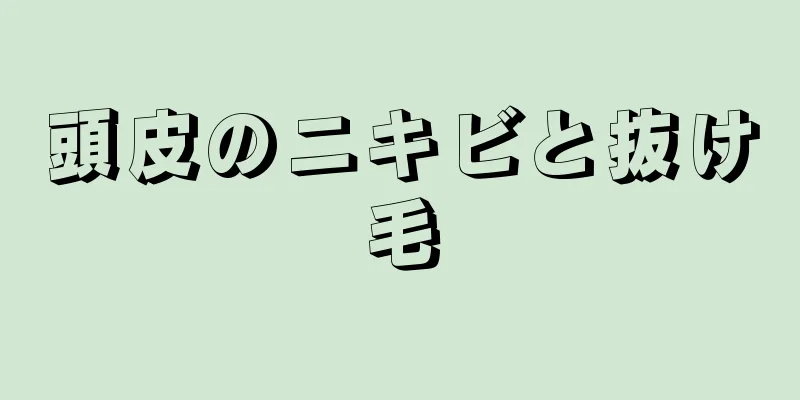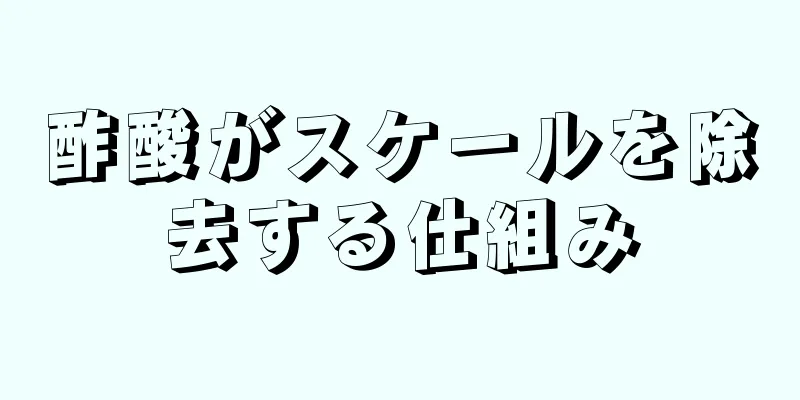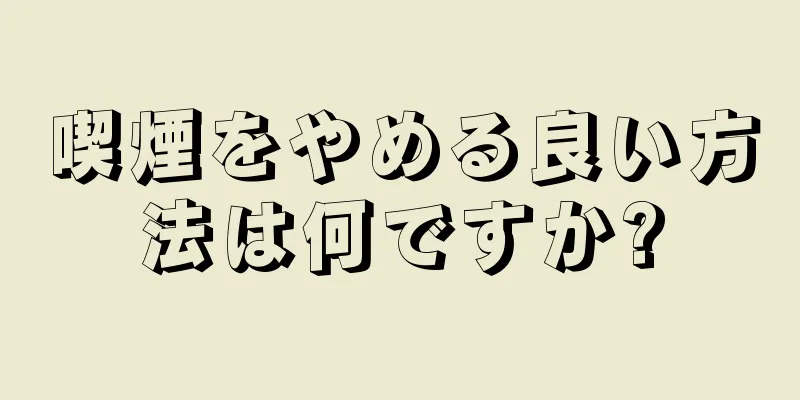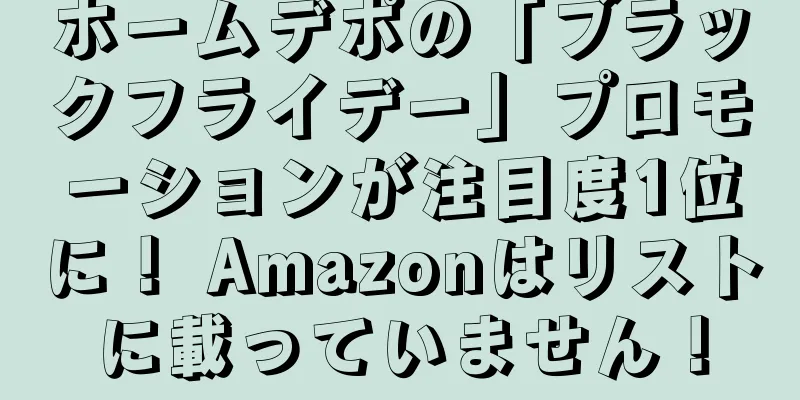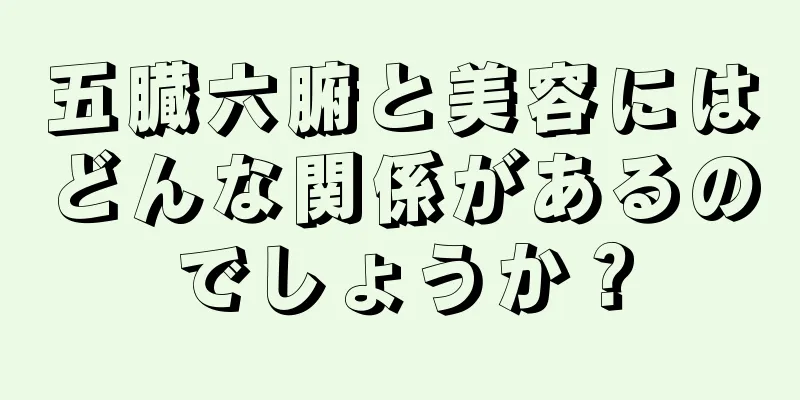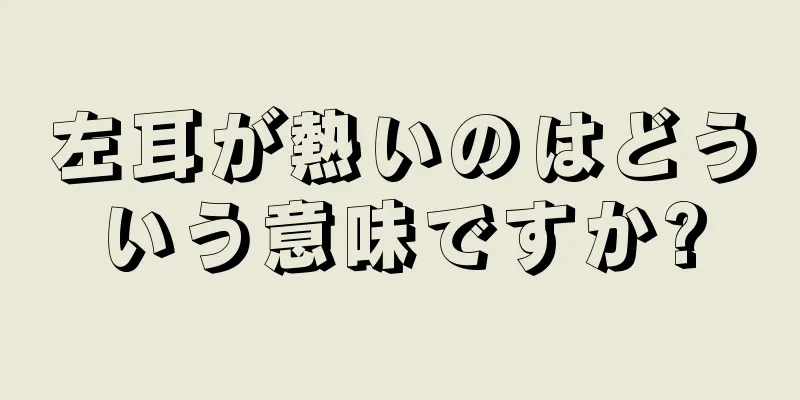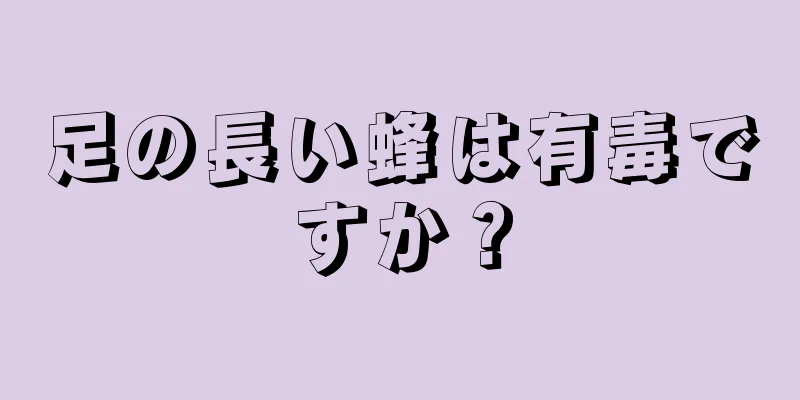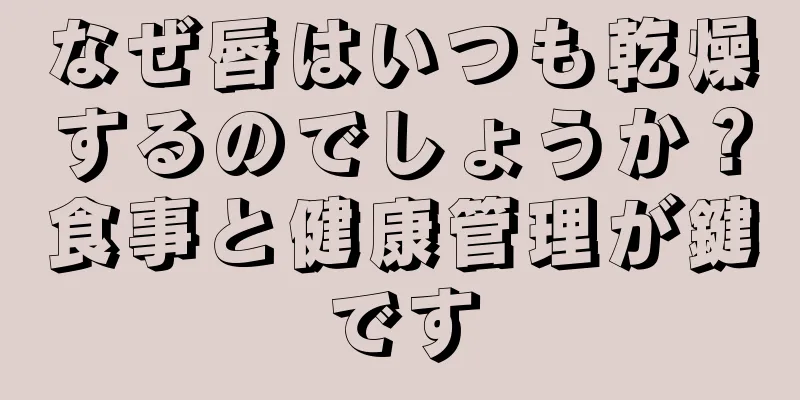肺吸虫を殺す方法
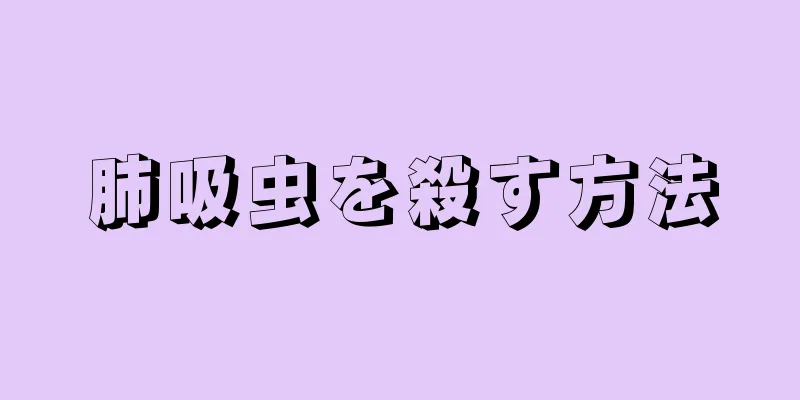
|
肺吸虫は人体に存在する異物であり、人体中を継続的に巡回し、さまざまな程度の損傷を引き起こします。人体の傷口に膿が出ると、その傷口から肺吸虫が体内に侵入します。寄生した肺吸虫を殺すのは非常に困難です。完全に駆除したいなら、まずは肺吸虫に関するいくつかのことを理解する必要があります。以下に肺吸虫を駆除する方法を紹介します。 肺吸虫症の臨床症状 1. 肺のタイプ 肺はウェステルマン肺吸虫が最もよく寄生する部位であり、最も一般的な症状は咳、血痰、胸痛です。典型的な痰は粘着性があり、ジャム状です。肺組織が壊死している場合は、痰は腐った桃のような血痰として現れます。 2. 腹部タイプ 腹痛は右下腹部によく見られますが、痛みの程度はさまざまです。下痢、肝腫大、血便、ゴマ状便がみられる場合もあり、その中に成虫や卵が見つかることもあります。明らかなしぶり腹感、身体検査時の腹部の圧痛があり、時には肝臓、脾臓、リンパ節の腫大、腹部の結節、腫瘤、または腹水がみられます。 3. 脳のタイプ ウェステルマン肺吸虫によって引き起こされることが多く、小児や若年成人に多く見られます。流行地域では発生率が 2% から 5% にも達することがあります。その症状には、頭痛、嘔吐、意識障害、視神経乳頭浮腫などの頭蓋内圧亢進の症状が含まれ、これらは初期の患者によく見られます。 4. 結節型 最も一般的な原因は肺吸虫であり、発生率は 50% ~ 80% です。腹部、胸部、背中、股間、太もも、陰嚢、頭頸部、眼窩、その他の体の部位に発生する可能性があり、大きさは大豆大からアヒルの卵大まであります。 肺吸虫症の治療薬 (1)ジクロロフェン硫酸塩(ベドリン):第一選択薬です。毒性が低く、経口吸収されやすいです。短期治癒率は84%~100%、長期有効性は80%~90%です。用量: 成人: 1 g、1日3回または1日おきに経口投与。10~20日の治療期間が1治療コースとなります。脳型の場合は、治療を2~3回繰り返すことができます。副作用には、めまい、頭痛、胃腸反応、発疹、まれにヘルクスハイマー反応などがあります。肝臓に障害が生じた場合は、直ちに薬の服用を中止してください。重度の心臓病、腎臓病、妊娠中の患者には禁忌です。 (2)プラジカンテル(EMBAY-8440):効果が高く、治療期間が短く、服用しやすく、副作用も少なく、軽いめまい、頭痛、倦怠感などがあるのみで、肺吸虫症の治療薬として有望である。投与量: 1回あたり25 mg/kg、1日3回、経口投与、2~3日間。脳型の患者は、1 週間の休止後に別の治療コースを受ける必要があります。 (3)ヘキサクロロパラキシレン(雪芳-846):肺吸虫症に対しても優れた治療効果がある。投与量:30 mg ~ 50 mg/kg、毎日または隔日で服用し、10 ~ 15 日間の治療コースとする。副作用としては、胃腸反応、頭痛、めまいなどがあり、まれに急性溶血性貧血や精神症状が起こることもあります。精神疾患の病歴がある人、重度の肝臓病や腎臓病のある人、妊娠中の女性には禁忌です。 |
推薦する
気血不足による便秘の治療法
気血不足による便秘を治療するには?便秘は非常に一般的な現象です。人生において、ほとんどの人は多かれ少...
腰痛の原因は?病気の要因に注意
疲労、寒さ、悪い姿勢などが原因で起こる腰痛は、休むことで改善することもあります。しかし、関節炎、腫瘍...
一日中心をリフレッシュするための小さな行動1つ
髪をとかしたり、目を回したり、噛んだり...これらはすべて私たちが日常生活で行う動作ですが、これらの...
洗濯洗剤は人体にどんな害を及ぼしますか?
洗濯用洗剤は生活必需品の一つと言えます。衣食住交通は人々の基本的なニーズであり、衣類は洗濯用洗剤で洗...
関連するブロックされたアカウントは自動的にブロック解除されますか?公式通知:国境を越えた詐欺にご注意ください!
先週の関連波の余波はまだ残っており、昨日の朝、Amazon からの通知が販売者に新たな重大な打撃を与...
乱視でもコンタクトレンズは装着できますか?
最近は携帯電話依存症の人が増えており、それに伴って近視の人も増えています。しかし、近視は比較的単純な...
咬筋肥大の原因
人間は食事をするときに常に噛む必要があります。噛むことができるのは咬筋があるからです。長時間、強く噛...
ヒトのニキビダニの治療方法
ダニは人々の日常生活のいたるところに存在すると言えます。自然環境中に存在するだけでなく、人の顔や体に...
非淋菌性尿道炎を治療する最良の方法は何ですか?
非淋菌性尿道炎は、日常生活でよく見られる病気です。初期症状は明らかではないため、人々に無視されてしま...
陰部がかゆい時の対処法
多くの女性が陰部のかゆみの問題に遭遇することがありますが、このとき女性はしばしば洗うことでそれを和ら...
間質性膀胱炎にはどのような薬を服用すればよいですか?また、症状は何ですか?
膀胱炎は誰もが聞いたことがあると思いますが、間質性膀胱炎についてはあまり馴染みがないかもしれません。...
皮膚アレルギー後に残ったメラニンを除去する方法
人間の皮膚に傷ができた時や、皮膚疾患による丘疹ができた時は、治った後も皮膚の表面にメラニンが残りやす...
腰を捻挫したらどうすればいい?
腰椎は人体の重心に位置し、日常生活では腰を支える必要があります。しかし、仕事中に腰を捻挫しやすくなる...
膣嚢胞の治療方法
恥骨壁嚢胞は、一般的に女性の膣内に現れる腫瘍を指し、一般的な臨床疾患でもあります。外陰嚢胞の発生には...
ヨモギと紅花の足湯の効能と役割、健康効果
最近では、多くの人が身体の健康を重視し、足を浸す習慣があります。定期的に足を浸すと、体全体の血液循環...