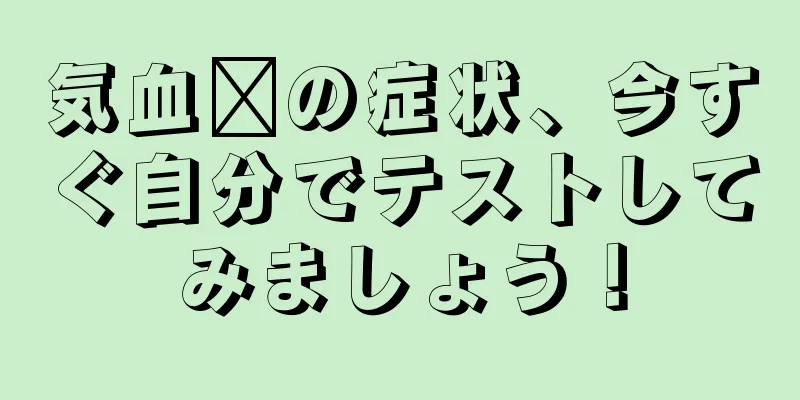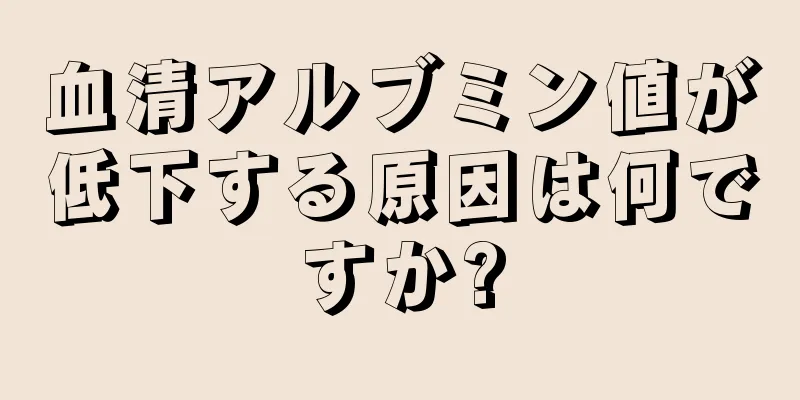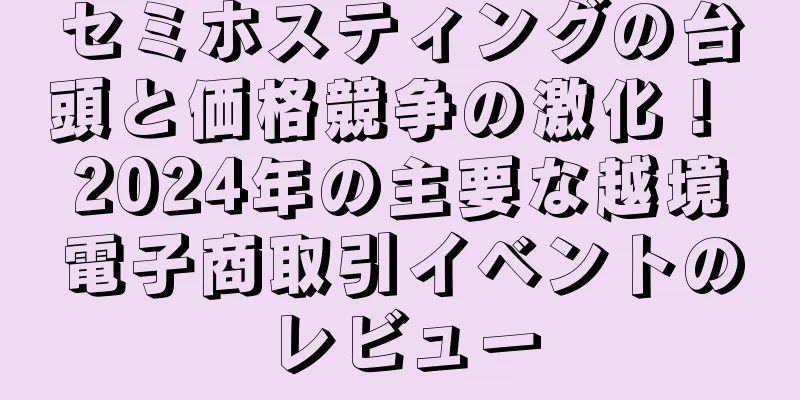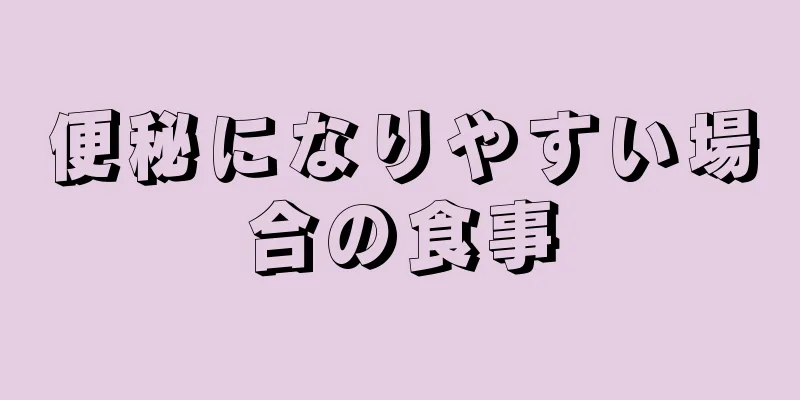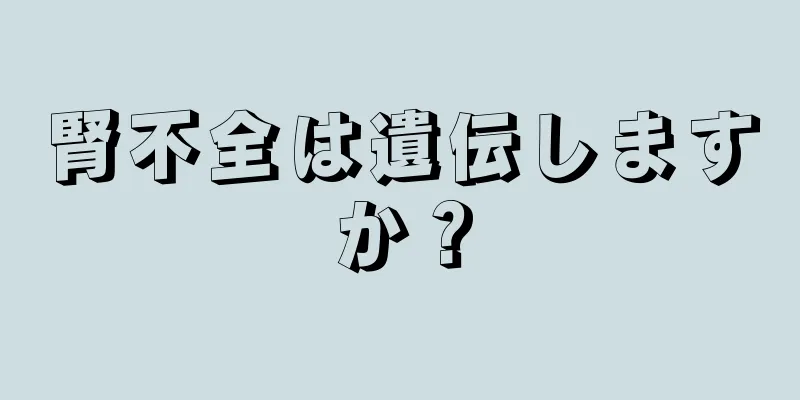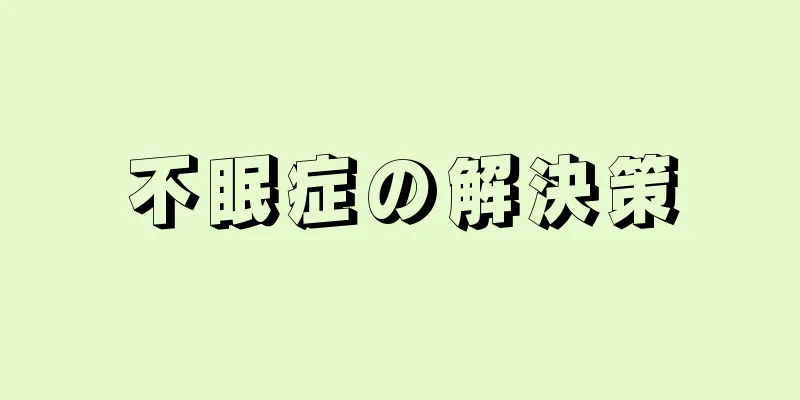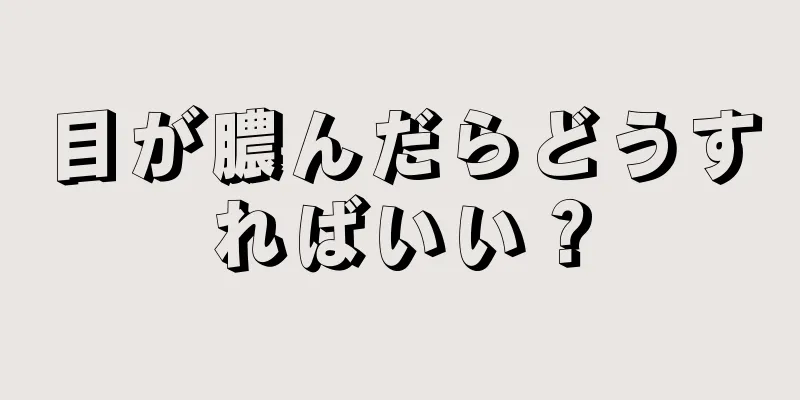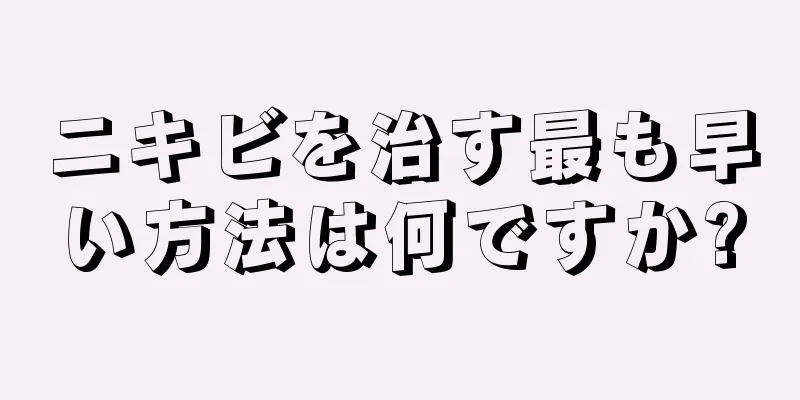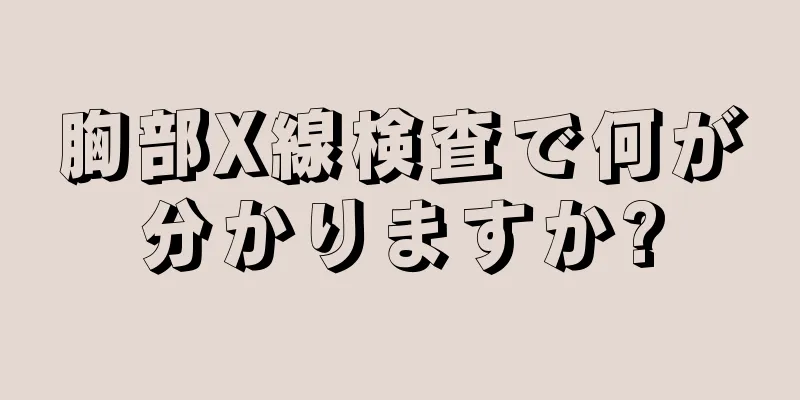目の隅に砂が入ったときのヒント
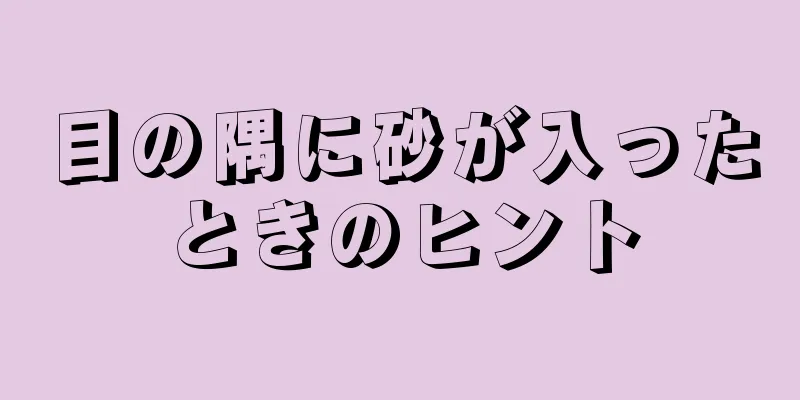
|
日常生活では、砂、ほこり、鉄粉などの小さなものが簡単に目に入ることがあります。一般的に、これらのものが目に入った場合、ほとんどの人は手で目をこすらずにはいられません。実は、これらは間違った方法です。目を強くこすると、角膜に埋め込まれやすく、感染症を引き起こし、ひどい場合は視力障害や失明を引き起こす可能性があります。 砂が目に入ったらどうすればいいですか? 砂が目に入ったとき、つい強くこすってしまう人が多いのですが、実はこれは間違いです。眼球の表面に浮遊している異物が角膜(黒眼球の表面層)に擦り付けられ、角膜を傷つけたり、角膜に埋め込まれて感染症や角膜潰瘍穿孔を引き起こす可能性があるためです。角膜潰瘍を引き起こす細菌には多くの種類がありますが、その中で最も毒性が強いのは緑膿菌です。不幸にしてこの細菌に感染すると、角膜潰瘍が発生すると、発症は急性で進行も速いです。適切な治療をしないと、短期間で角膜潰瘍が穿孔したり、失明につながることもあります。 砂が目に入ってきたときの正しい対処法は何ですか? 目を軽く閉じ、ゆっくりと目を半分開け、この動作を 2 ~ 3 回繰り返します。ほとんどの場合、涙が流れると砂は洗い流されます。砂がまだ目の中に残っている場合は、誰かに調べてもらうか、病院に行って砂がどこにあるのか調べてもらう必要があります。砂がまぶたの内側または白目の表面に付着している場合は、滅菌綿棒または清潔なハンカチで優しく拭き取ってもらうように頼んでください。 正しい手順 1. 角膜の損傷を防ぐため、砂やほこりが目に入った後は目をこすらないようにしてください。 2. 砂やほこりが目に入った場合は、上まぶたをそっと持ち上げて数回引っ張り、涙で洗い流し、眼球を回転させてから、患者に目を開けさせます。これにより、異物が目から排出されることがよくあります。 3. 砂やほこりが目に入った場合は、上まぶたを開けます。まぶたを開ける際は、患者に下を向くように指示します。救急救命士は親指と人差し指で上まぶたをつまんで少し前に引っ張り、親指を人差し指で軽く押して上方に回します。異物を見つけて、ピンセットや湿らせた綿棒、濡れたハンカチで取り除きます。角膜を傷つけないように、乾いた布で眼球を拭かないでください。異物を見つけるには、懐中電灯やスポットライトの助けが必要になる場合があります。 4. 目の中にゴミが入って異物を取り除いた後、沸騰したお湯または生理食塩水で目を洗い、点眼薬(軟膏)を塗ってください。 5. ほこりが目に入った後、上記の手順で角膜を傷つけてはいけません。 6. 粉塵が目に入ってしまい、異物が除去できない場合は、直ちに病院に搬送する必要があります。 緑膿菌感染症は毒性が強いものの、その侵入能力は非常に弱く、角膜に侵入するには損傷した表面上皮を通過する必要があることに留意する必要があります。したがって、砂が目に入ってしまった場合は、角膜上皮を傷つけないように目をこすらないでください。これが緑膿菌角膜潰瘍を予防する鍵です。 |
推薦する
生姜を塗ると髪の成長に役立ちますか?
生姜は生活の中で最も一般的な調味料の 1 つです。生姜は植物の根茎で、辛くて刺激的な味がしますが、生...
正常な尿には泡がありますか?
尿に泡が出るとタンパク尿になるという話を聞いたことがある人もいるでしょう。実は、正常な人の尿にも泡が...
ニキビやニキビ跡を除去するためのヒントは何ですか?
人は一定の年齢に達するとニキビができやすくなります。ニキビには特定の毒素が含まれているため、適切な時...
目の周りで汗が出る原因は何ですか?
非常に暑い天候などにより、人体は頻繁に汗を排出しますが、これは正常な現象です。しかし、天候以外の原因...
Amazon で模倣者を捕まえて手数料を変更する 15 の方法
手数料の変更は現在カナダのサイトに適用されますアメリカは今変わることはできないヨーロッパのサイトは不...
桑の根のタブー
桑の実を食べたことがある人は多いと思います。成熟した桑の実は濃い紫色で、甘酸っぱい味がしてとても美味...
ヘアマスクの用途は何ですか?ヘアマスクの正しい使い方
ヘアマスクは、よく使われるヘアケア商品です。正しく使えば髪質を良くすることができますが、使い方を間違...
レーザー脱毛後に注意すべきことは何ですか?
レーザー脱毛は、非常に人気のある現代の脱毛技術です。この技術は非常に先進的で、身体に外傷を与えること...
エアコンを使うと顔がむくむのはなぜですか?
夏は気温が非常に高く、汗をかきやすく、非常に不快に感じます。そのため、夏には多くの人がエアコンの効い...
看護師のための基礎知識
看護師は人生になくてはならない存在であることは誰もが知っています。一般的に看護師は女性です。女性に比...
出産後、母乳が出るまでどのくらいかかりますか?
新生児の主な栄養源は母乳であり、赤ちゃんは出産後すぐに授乳する必要があります。通常、女性は出産後に母...
眼感染症の症状の原因は何ですか?
目は人体の中で最も傷つきやすい部分です。目の衛生に注意を払わず、頻繁に手で目をこすると、細菌やウイル...
アレルギーがある場合、ヨモギで顔を洗っても大丈夫でしょうか?
ヨモギは漢方薬として広く使用されている漢方薬であり、ヨモギから作られた漢方薬丸薬や灸棒は人体に優れた...
ポニーテールをシンプルかつ美しく結ぶにはどうすればいいでしょうか?
女の子の髪は一般的に長いので、非常に人気のあるポニーテールを含む多くのヘアスタイルを作るのが簡単です...
水分含有量が多い果物は何ですか?
体内に水分が多い人は、むくみを感じます。一般的に、水分は悪い生活環境や食生活によって生じます。水分の...