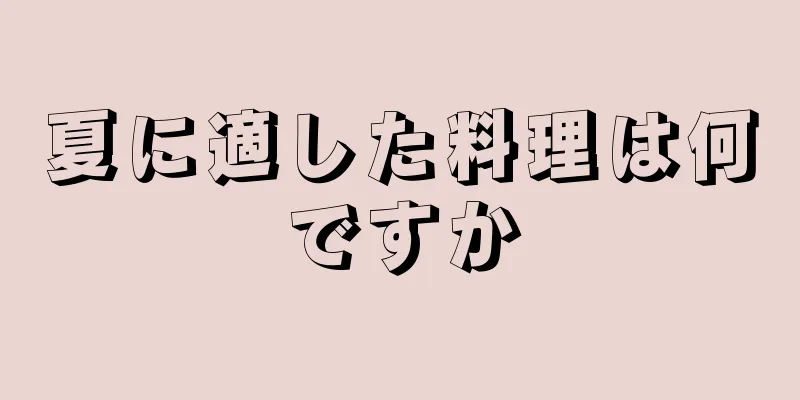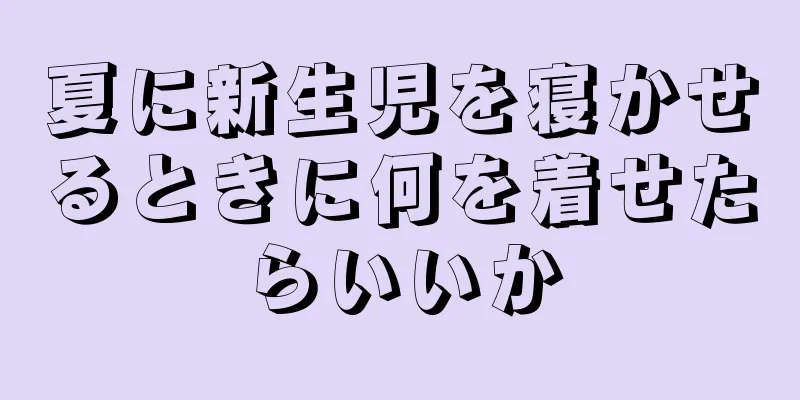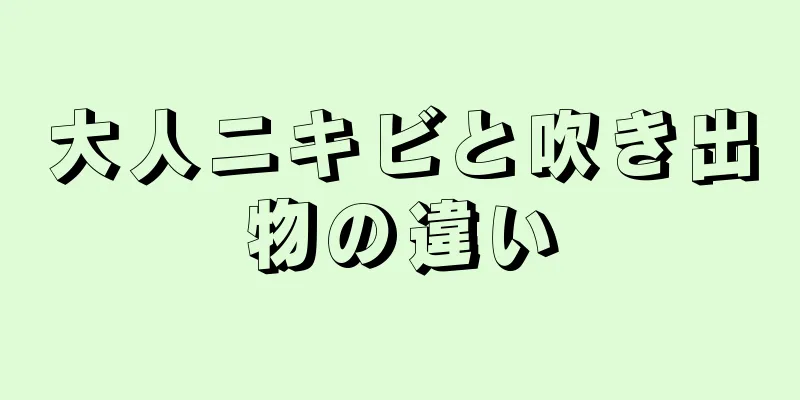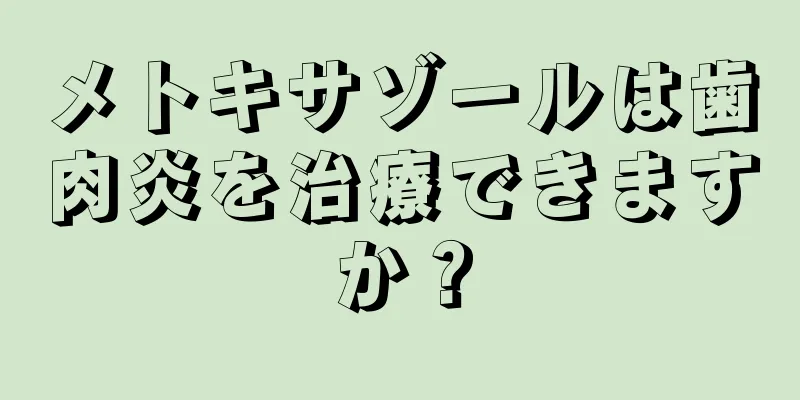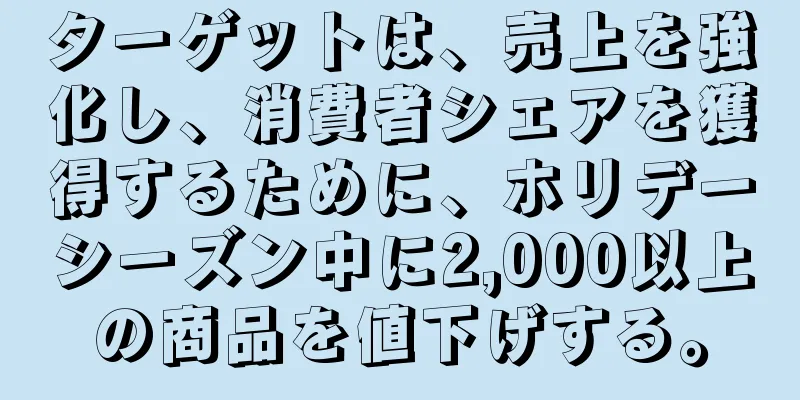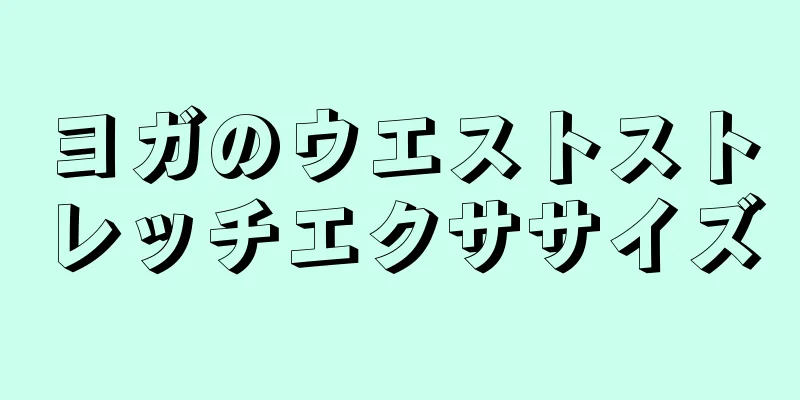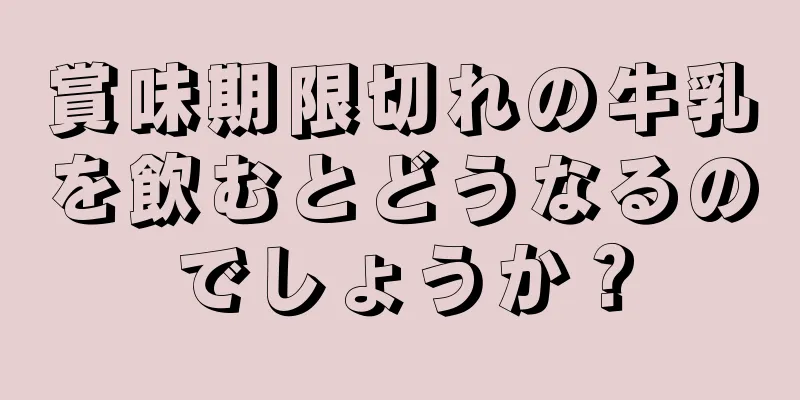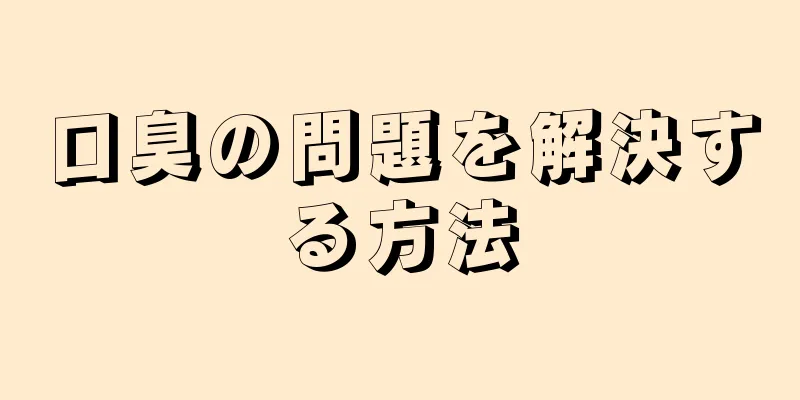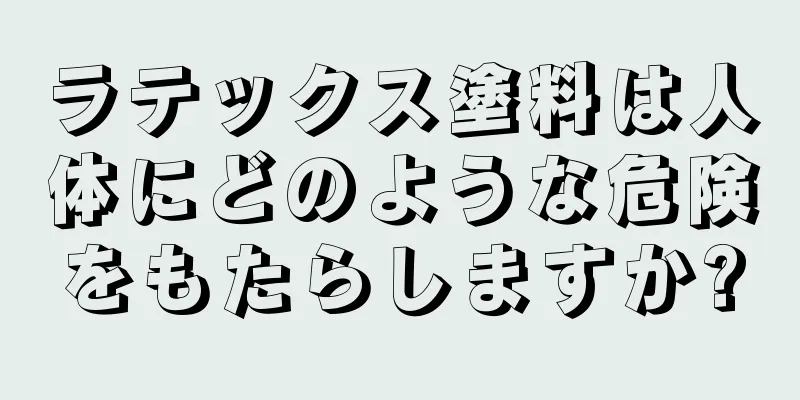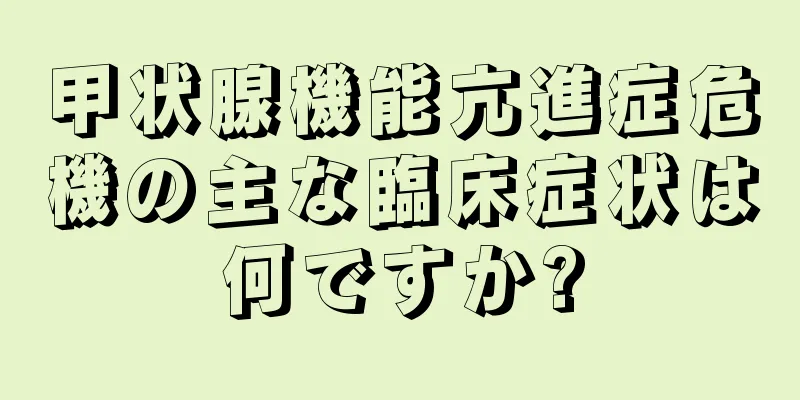翌日また髪を染めてもいいですか?
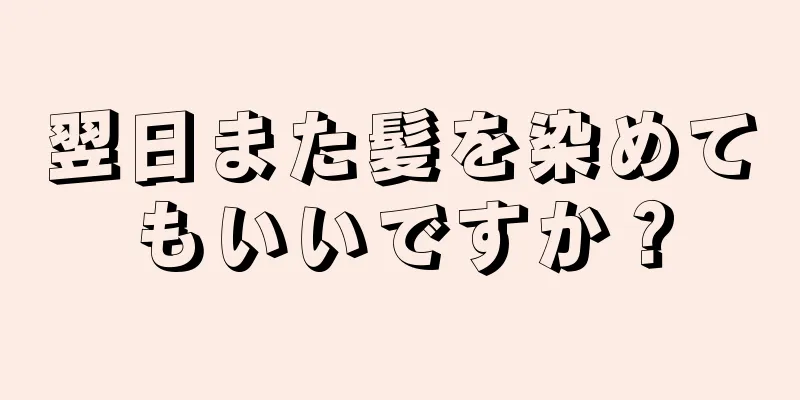
|
自分自身を大切にすることは、おそらくすべての女の子がたゆまぬ努力を続けている課題でしょう。誰もが頭からつま先、髪の毛に至るまで、自分のあらゆる面に細心の注意を払っています。多くの女の子は髪を染めるのが好きですが、染色中に何らかのミスをすると、望み通りの効果が得られない場合があります。このため、多くの人が髪を再び染めることで状況を改善したいと考えています。しかし、翌日に髪を染めることは本当に可能なのでしょうか? 2回続けて髪を染めることは、髪に非常に有害です。複数回染めると頭皮が刺激され、髪質に影響します。少なくとも年に1回は髪を染めることをお勧めします。頻繁に髪を染めないでください。髪の健康とケアに注意し、軽めの食事をとり、高カロリーまたは刺激のある食べ物を避け、十分な睡眠を確保してください。 ヘアカラーの注意事項: 1. 3トーンより明るくない髪色を選ぶ 染髪の原理は、髪を守っているキューティクルを開き、髪本来の色を取り除き、その後染髪剤の色を加えることです。そのため、ヘアカラーの色を選ぶ際は、元の髪の色より最大でも 3 度明るい色にする必要があります。そうでないと、髪にかなりのダメージを与えてしまいます。より明るい色にしたい場合は、1か月半以上の間隔をあけて、数回に分けて髪を染めるのが最適です。 2. 染める前に必ず髪を洗ってください 髪を染める前に、髪がきれいで、ムースやヘアスプレーなどのスタイリング剤が付いていないことを確認してください。また、パーマは必ず髪を染める前に行い、その間に1週間の間隔を空ける必要があります。アレルギー性皮膚の場合はアレルギー検査を受ける必要があります。 3. 耳にかかるくらいの短い髪の場合は、染毛剤1箱で十分です。ミディアムから肩までの長さの髪の場合は、染毛剤を 1 ~ 2 箱使用しますが、ロングヘアの場合は、2 ~ 3 箱必要になる場合があります。 4. 髪を染めるときは室温を20℃に保ちます。 5. 髪を染めたばかりの場合は、高温により髪に深刻なダメージを与える可能性があるため、電気ヘアアイロンやその他の美容器具を使用しないでください。 6. 髪を洗うときは温水を使用してください。高い水温で髪が色あせてしまうのではないかと心配して、冷たい水で洗う人もいます。それもまた正しくない。髪を洗うときに冷たすぎる水を使用すると、シャンプーやコンディショナーの不純物が髪の鱗に閉じ込められ、洗い流すことができません。時間が経つにつれて、髪は硬くなってしまいます。 7. シャンプーを選ぶときは、中性のものを選ぶようにしてください。そうでないと、アルカリ性のシャンプーは髪の色落ちを引き起こしやすくなります。ヘアカラー剤は、色が鮮やかであるほど分解されやすく、アルカリ性のシャンプーは、もともと不安定な赤色などの色をさらに褪色させる原因となります。コンディショナーは酸性なので、使いすぎると色落ちしやすくなるので、染めた髪専用のコンディショナーを選ぶようにしましょう。 |
推薦する
足を浸すのに最適な時間は何時ですか?
多くの人にとって、足湯は健康的なライフスタイルであり、体の調整に大きな効果があり、特に冬場は効果がよ...
運動後の膝の痛みを和らげる方法
運動後の膝の痛みを和らげる方法運動後の膝の痛みは、不適切な運動によって引き起こされる傷害です。このと...
耳たぶの下に硬いしこりができる原因は何ですか?
耳たぶの下に硬いしこりができたら、暑さが原因かどうかに注意する必要があります。通常、暑すぎると体自身...
鹿のペニスでワインを作る方法
鹿のペニスは日常生活にとても役立ちます。実は鹿の外部生殖器官です。薬効があるだけでなく、食用価値も高...
牛乳を飲んだ後に桃を食べてもいいですか?
すべてのものは相互に強化し、相互に抑制し合っています。一緒に食べてはいけない食べ物はたくさんあります...
好中球数の低下とは何ですか?
定期血液検査の項目の一つに好中球数があり、そのレベルは私たちの健康と一定の関係があります。好中球の値...
ジーンズの色褪せを防ぐ方法
ジーンズの色落ちの問題は非常によくあります。ジーンズの色あせを防ぐ方法、今日はジーンズの色あせを防ぎ...
ペディキュアをするのに最適な時期はいつですか?
足マッサージは、多くの人が睡眠を促進し、冬の風邪を和らげるために選ぶ方法ですが、足マッサージの時間の...
マザーワート足湯の効能
マザーワートについてあまり知らない人もいると思いますが、もちろん、もっとよく知っているべき人もいます...
精巣外傷の痛みの症状
人生では、予期せぬ出来事に遭遇することがあります。男性の中には、精巣外傷を患い、痛みを感じる人もいま...
ほとんどの人が知らないクルミ材の医学的効果
クルミ材はクルミの木から切り出された木材で、独特の医療効果があります。クルミ材で作られた木製の櫛は、...
針生検は痛いですか?
穿刺生検は、さまざまな臓器に異常がないか、どのような異常があるのかを調べる検査法で、臨床医学で広...
毎朝起きると腰の両側に痛みがあります
通常の状況では、腰が痛くなることはありませんが、腰を使いすぎたり、同じ姿勢を長時間維持したりすると、...
リンゴの筋肉の顔の形は何ですか
リンゴの筋肉は筋肉ではなく、頬骨の脂肪組織であるため、リンゴの筋肉は顔の形を表現できません。リンゴ筋...
椎間板ヘルニアは自然に治りますか?
仕事や生活習慣のせいで、椎間板ヘルニアという病気に苦しむ人が増えています。多くの場合、椎間板ヘルニア...