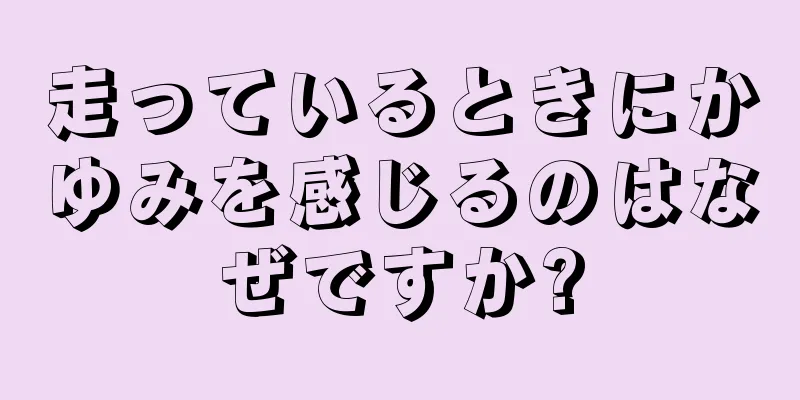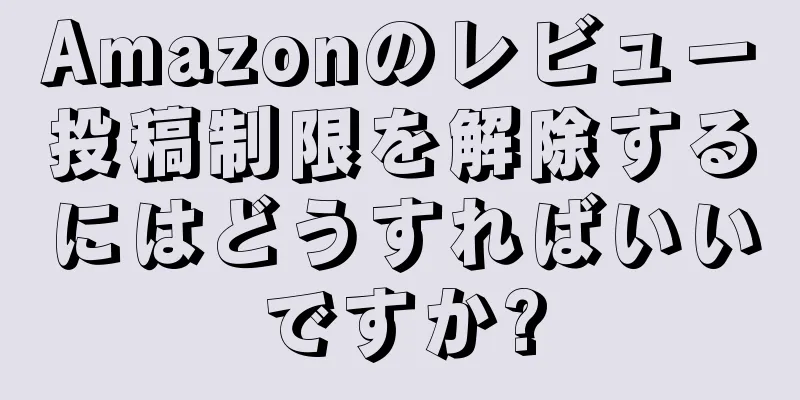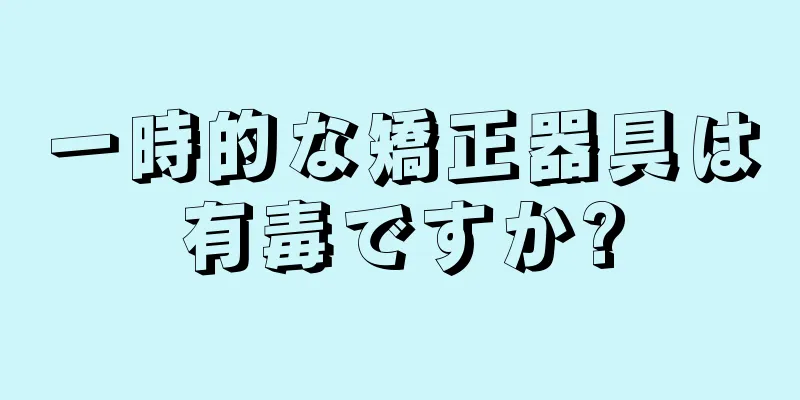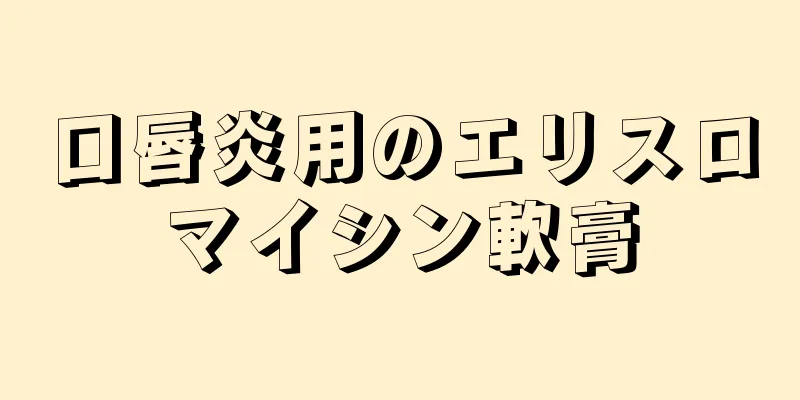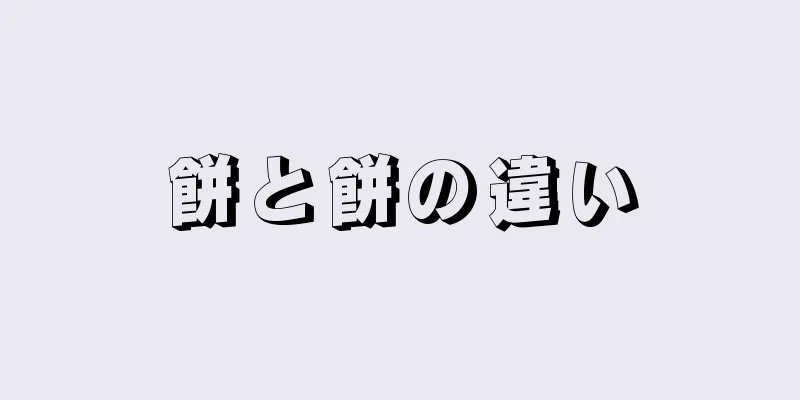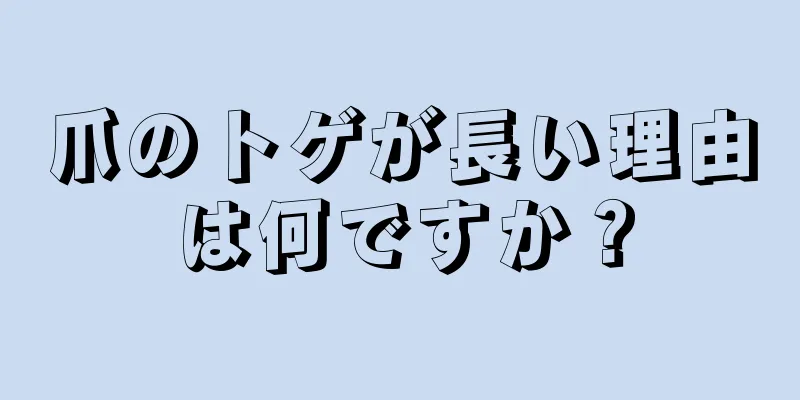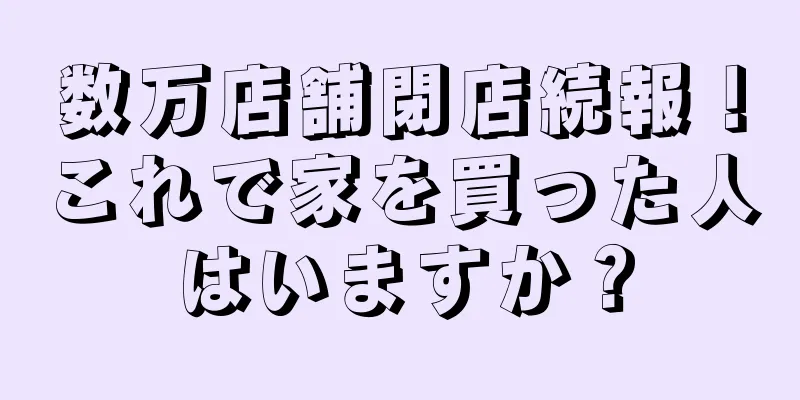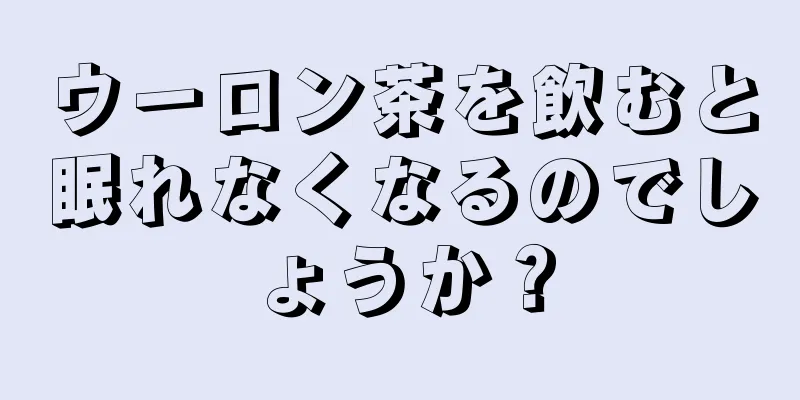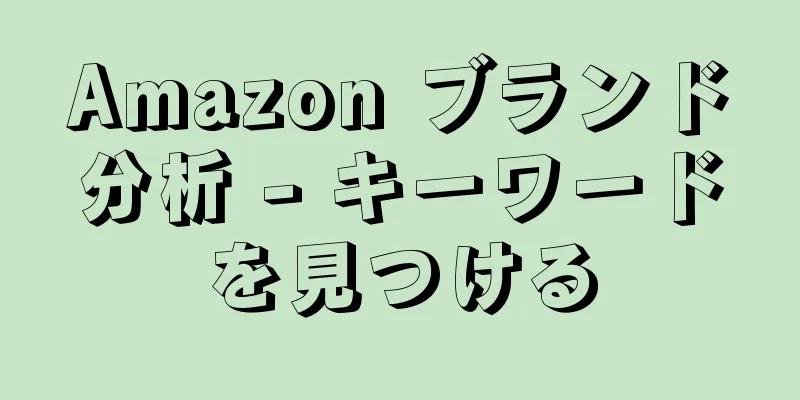狭心症が起こったときの対処法とその緩和方法
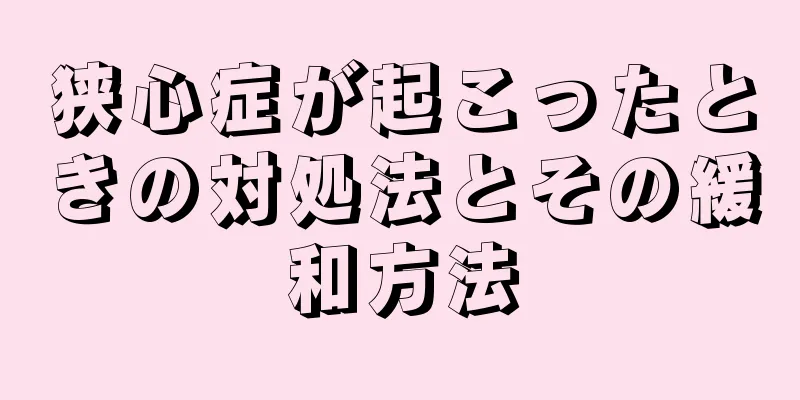
|
狭心症は顕著な痛みを引き起こし、まるで心臓が圧迫されているように感じられます。狭心症が重度の場合は、致命的となる可能性があります。狭心症になった場合、症状を緩和して良くなるように何らかの対策を講じる必要があります。 1. 初めて狭心症発作を起こした場合の対処法 初めて狭心症を発症した患者は、救急薬を携帯していないことがよくあります。このような状況に遭遇した場合、危険を過度に心配する必要はありません。突然の狭心症は10分以上続くことがほとんどなく、心筋梗塞を経験した人は狭心症の発作を頻繁に起こした経験があります。したがって、初めて突発性狭心症を発症した患者にとって、救急薬がない場合、最も効果的な応急処置は、直ちに活動を中止し、その場で休息し、心を落ち着かせることです。 2. ニトログリセリンを舌下摂取する 冠状動脈疾患の患者は通常、緊急用医薬品を携帯しています。狭心症が起こったら、すぐにニトログリセリンの錠剤を取り出し、噛み砕いて舌の下に置きます。通常、痛みは約 2 分で緩和されます。効果が得られない場合は、10分後にもう1錠服用してください。ただし、狭心症が改善するか再発するかに関わらず、ニトログリセリンを3錠以上継続して服用することはお勧めできませんので、ご注意ください。 3. すぐに休憩を取る 狭心症が起こると、患者は突然、胸骨の下に新たな持続的な圧迫感や窒息感を感じます。このようなことが起こった場合、患者は直ちにすべての活動を中止し、落ち着いて座って休む必要があります。 4. 耳鍼 病院以外の場所で突然狭心症が発症し、救急医療も近くにない場合、最も簡単で効果的な方法は「耳ツボ押し」です。狭心症の患者の耳のツボを押すと、痛みがすぐに和らぎ、症状が緩和されます。具体的な方法は以下の通りです。 1. マッチ、つまようじ、または細い枝、または小さくて長い釘を用意します。 2. 針の先端を使って、患者の耳介の耳たぶの真ん中にある最も敏感な痛みのポイント(耳の中心点)を感じます。 3. 細い棒を持ち、痛みのある箇所を少し力を入れて押します。約1分で鎮痛効果が現れ、2~3分で狭心症が緩和されます。 |
<<: 干しエビをもっと食べたほうが良いのでしょうか?なぜですか?
推薦する
越境EC事業者が注目すべき54のKPI
KPI は、e コマース販売者の最良の味方であり、店舗のトラフィック、売上、顧客サービス、マーケテ...
首の前方矯正方法
首の伸展は、主に長期間の間違った座り方や立ち方によって引き起こされ、特に、10代の若者や、長時間デス...
耳の後ろの痛みの原因は何ですか?
耳の健康にも注意と保護が必要です。適切に保護しないと、中耳炎、外耳炎、耳ヘルペスなどの病気にかかりや...
米国オンラインショッピング返品現状調査:消費者は送料負担に前向き!
スマートな電子商取引返品プラットフォームであるLoopの新しい調査によると、米国のオンライン消費者の...
耳鳴りはどんな病気の症状ですか?
脳は人体の中心的な処理・制御センターであり、体のさまざまなシステムの指揮を担っています。したがって、...
米国のオンライン小売売上高は、感謝祭のショッピング週末の好調により、12月に前月比4.5%増加した。
1月14日、海外メディアの報道によると、全米小売業協会(NRF)が発表した月次小売監視報告によると...
匂いに対する敏感さの原因は何ですか?
多くの人は非常に鋭い嗅覚を持っており、特に匂いに敏感です。一般的に、女性は妊娠すると匂いに対して特に...
ストレスを解消する最良の方法
現代を生きる人々は、社会の急速な発展、経済構造の変化、人間関係の変化などにより、就学や就職などさまざ...
細胞再生と修復療法
細胞再生修復療法は、中枢神経系細胞の損傷、臓器の損傷、免疫系疾患を治療できる医療方法であり、小児脳性...
みかんの皮の特性と経絡
みかんの皮は一般的な漢方薬です。加工したオレンジの皮から作られ、気を調整し、脾臓と胃を強化する機能が...
目やにが頻繁に出る理由は何ですか?
多くの人が頻繁に目やにが出ることに困惑し、恥ずかしい思いをしています。そのため、問題を効果的に解決し...
食道憩室は深刻な病気ですか?
食道憩室は一般的に良性の病変を指しますが、人体への影響も比較的大きく、嚥下障害を引き起こすことがよく...
設定料なし - 発送方法の作成
設定料なし - 発送方法の作成以下のコンテンツをすべて入手したい場合は、公式アカウントの記事を友人グ...
LED 目の保護ランプは本当に目を保護しますか?
現在、視力を保護することができる一種のLED眼保護ランプが市場に出回っていますが、専門家のアドバイス...
フラフープは減量に役立ちますか?
フラフープはウエストを細くするのに役立ちますか? 誰もが美しさを愛しますが、美しさには完璧な体型も含...