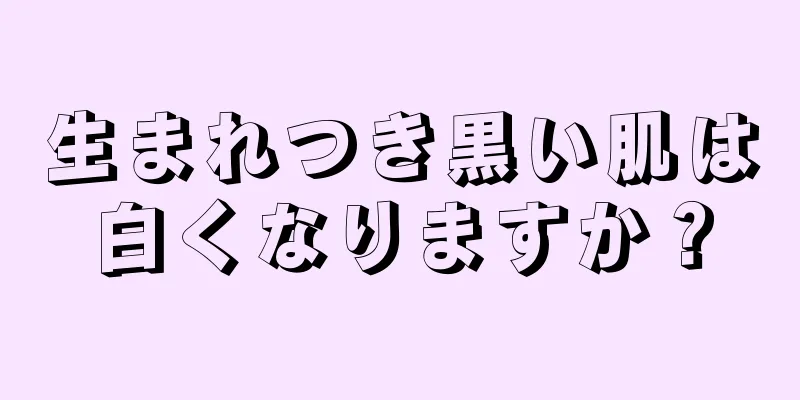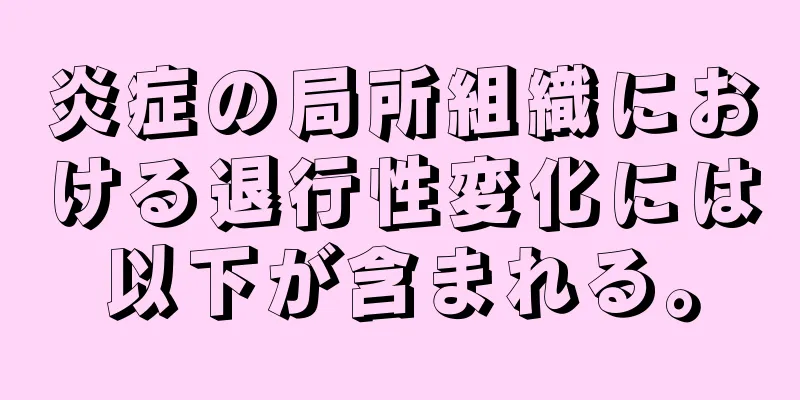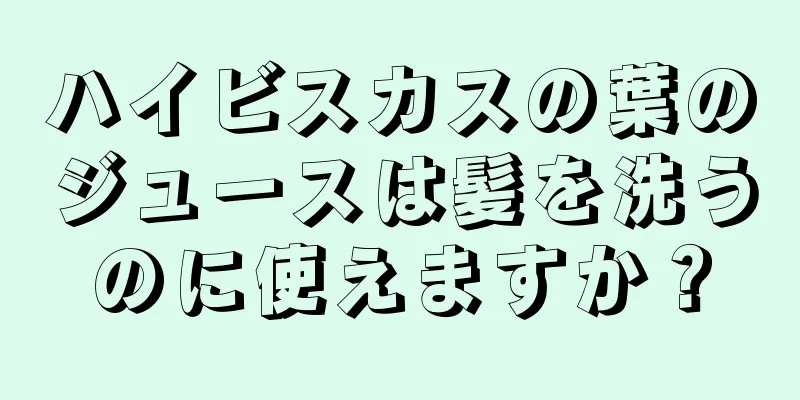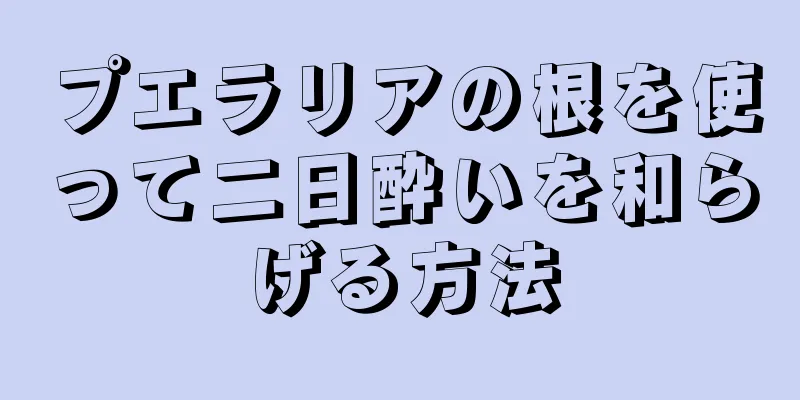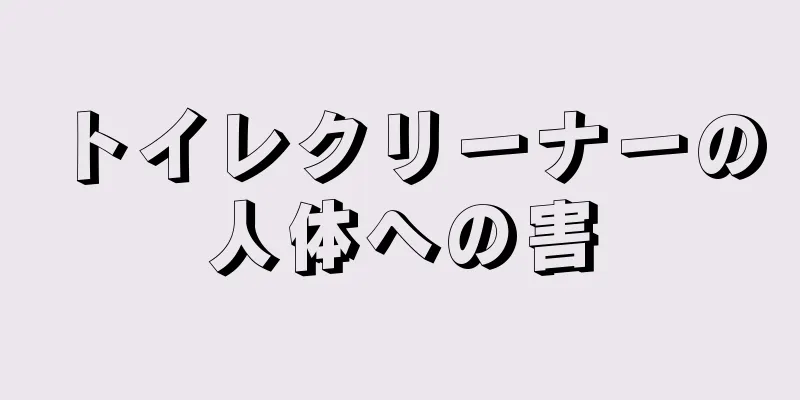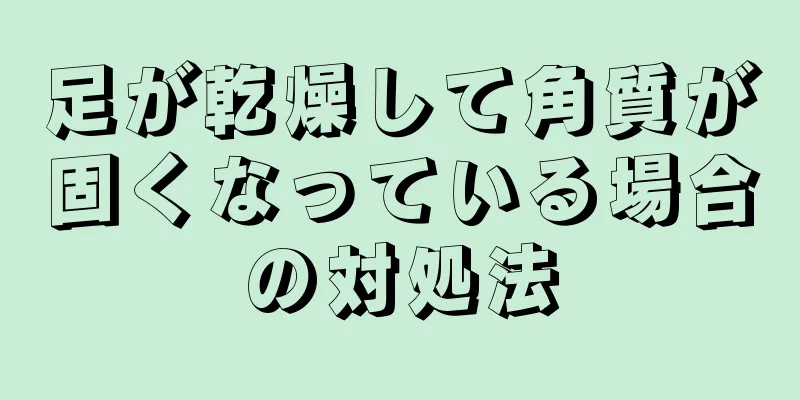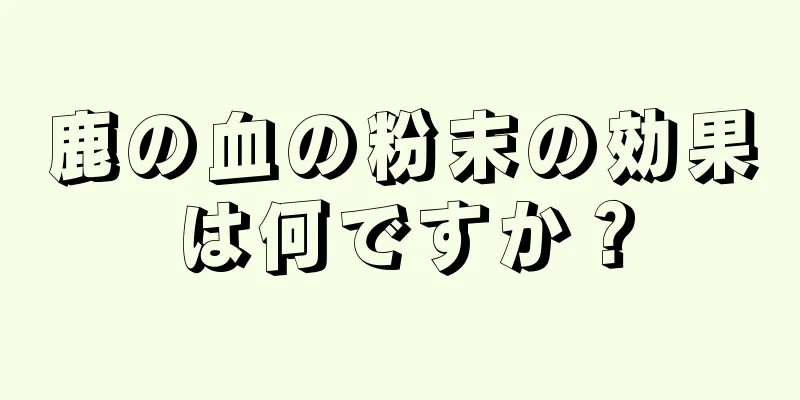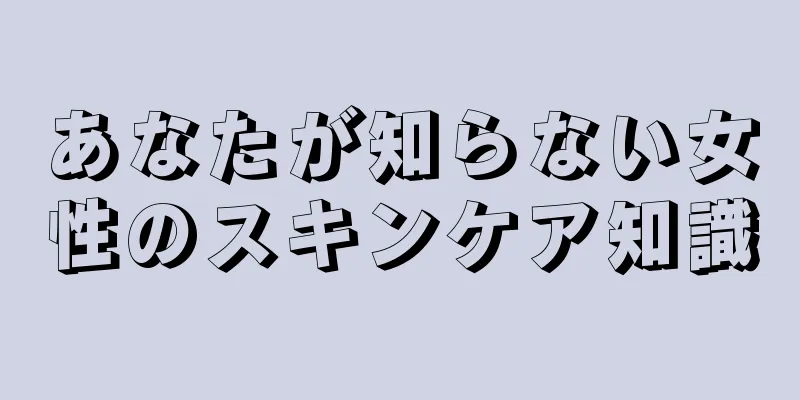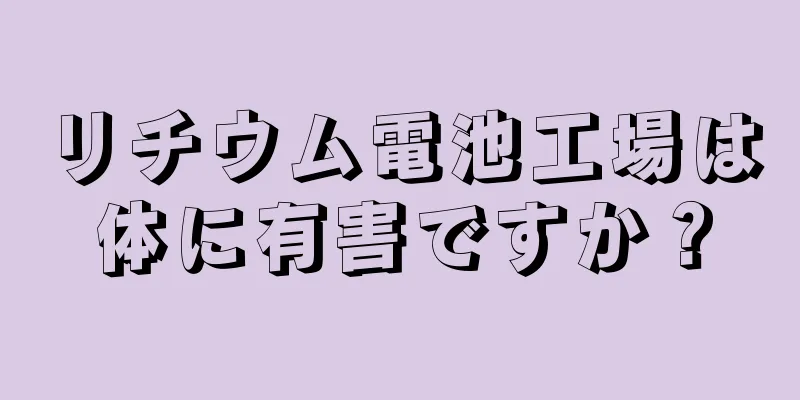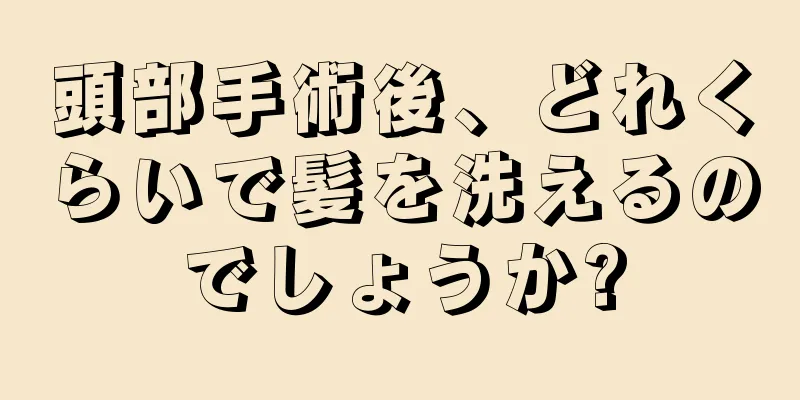アロエベラはおたふく風邪の治療に効果がありますか?
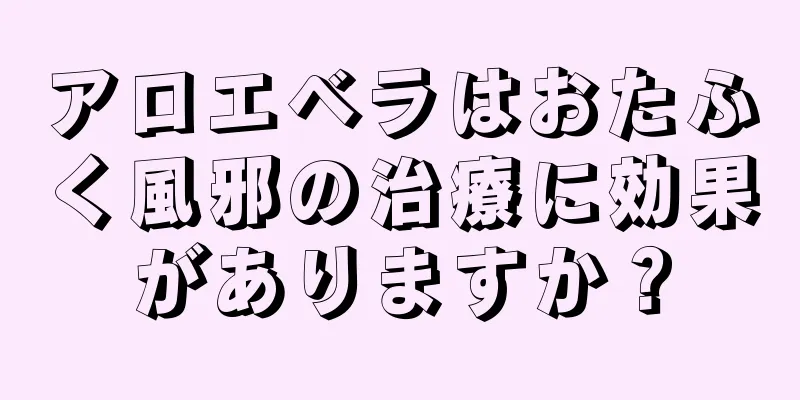
|
おたふく風邪の影響は比較的大きいです。アロエベラはおたふく風邪の治療に効果的だと考える人もいますが、実際にはこの方法は局所的な痛みを軽減・緩和するだけで、治癒することはできません。対症療法、水分と電解質の補正、抗菌薬の正しい選択に注意する必要があります。 1. 化膿性耳下腺炎 (1)原因を治療し、水分、電解質、酸塩基のバランスを是正する。 (2)有効な抗菌薬を選択し、ペニシリンまたは第一、第二世代セファロスポリンなどのグラム陽性球菌に対する抗生物質を大量に経験的に使用します。耳下腺管開口部から膿を採取し、細菌培養と薬剤感受性を調べ、薬剤感受性に基づいて感受性抗生物質を調整します。 (3)その他の保存的治療:炎症の初期段階では、温湿布、理学療法、外用などが用いられる。重曹水やオーラルケアなどのうがい薬は炎症を抑えるのに役立ちます。 (4)保存的治療が無効で化膿した場合は切開排膿が必要となる。 2. おたふく風邪 (1)耳下腺の腫れが完全に治まるまで隔離し、安静にする。口腔衛生に注意し、酸性の食品を避け、水分を摂取するようにしてください。 (2)対症療法が主な治療法であり、抗生物質は効果がない。リバビリンを試すこともできます。インターフェロンが効果的だという報告もあります。 (3)副腎皮質ホルモン療法は明確な効果はないが、重篤な場合や髄膜脳炎、心筋炎などの合併症がある場合には短期的な使用が考慮される。 (4)おたふく風邪の治療においてヘリウムネオンレーザーによる局所照射は、痛みや腫れの緩和に一定の効果がある。 (5)成人男性患者は、睾丸炎の発症を予防するために、病気の早期段階でジエチルスチルベストロールを使用する必要があります。 (6)伝統中国医学:内服の場合、症状に応じて修正を加えながら、普済小当陰処方を主処方とする。局所適用の場合、酢に混ぜた紫金錠または青岱粉を1日1回外用します。 |
推薦する
結核の薬を服用した後に関節痛が起こった場合の対処法
いくつかの薬は病気を緩和することができますが、私たちの体に特定の影響を及ぼすこともあります。これらの...
ザクロは体内の熱を引き起こしますか?
ザクロは私たちの生活の中で非常に一般的な果物です。この果物は通常秋に熟します。熟したザクロは非常に甘...
胃風邪の症状は何ですか?
現代では、多くの人が胃腸の不調に悩まされています。主な理由は、生活のペースが速まっていることです。日...
成熟した人と未熟な人の違い
人には必ず未熟な段階があります。未熟さの表れは幼稚さです。物事のやり方が場違いに見えます。自分自身の...
水を飲んだり食べたりするときに汗をかくのはなぜですか?
体力の弱い人は、細菌に対する抵抗力がないため、常に体に小さな問題が生じます。体力の弱い人の多くは、め...
Platycladus orientalisの葉の機能と効果はこれらの病気を治すことができます
キキョウの葉はキキョウ葉とも呼ばれ、止血、リウマチの解消、痰の解消、咳の緩和などの効能があり、喀血、...
酢を使って歯についたタバコの汚れを落とす方法
日常生活では、多くの食習慣や日常の習慣が歯に何らかの影響を与えます。日常生活で歯のケアに気を配れば、...
天津で食事をするのに良い場所はどこですか?
どの場所にもその土地ならではの食べ物があり、地元の食べ物は他の場所では作りたくても作れないものです。...
ブドウを食べるとき、種を吐き出しますか?
ブドウは栄養が豊富で、食べることで体に栄養を吸収させることもできます。ブドウは皮をむいて種を吐き出さ...
性器のかゆみの原因は何ですか?
男性と女性の生殖器官は特殊なため、環境や長時間労働などにより必ず問題が生じます。その中には、生殖器に...
産後休暇中にどのようなサプリメントを与えるべきでしょうか?
あなたの周りに産後産後産後産後の女性の友人がいる場合、誰もが彼女に会いに行くことを考えますが、多くの...
痔と便秘の外的症状は何ですか?
痔疾になると、血便、痛み、腫れ、痒みなどが生じやすくなるほか、便秘になりやすいという明らかな症状も現...
タンパク尿とは何ですか?
タンパク尿とは何ですか? 尿タンパクと診断された後、多くの友人がこの質問をするでしょう。いわゆる尿タ...
ゴールデンシーバックソーンオイルの効能
ゴールデンシーバックソーンオイルの効果には、心臓血管系と脳血管系の保護、呼吸器疾患の予防、脳の発達の...
両眼屈折異常の症状は何ですか?
両眼屈折異常の一般的な症状は近視であり、軽度近視と重度近視に分けられます。また、視覚疲労などのさまざ...