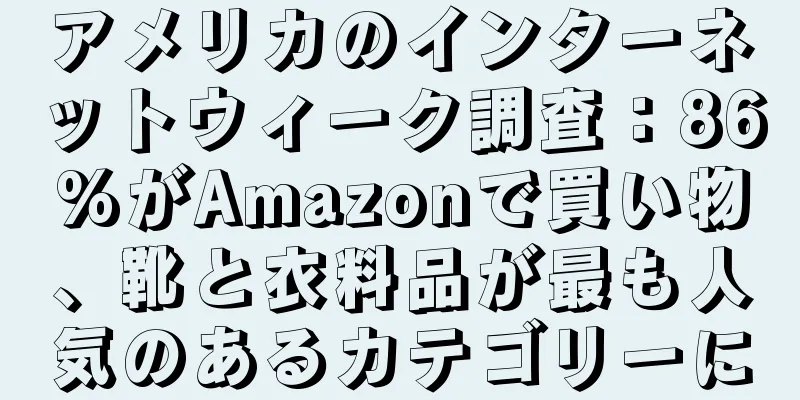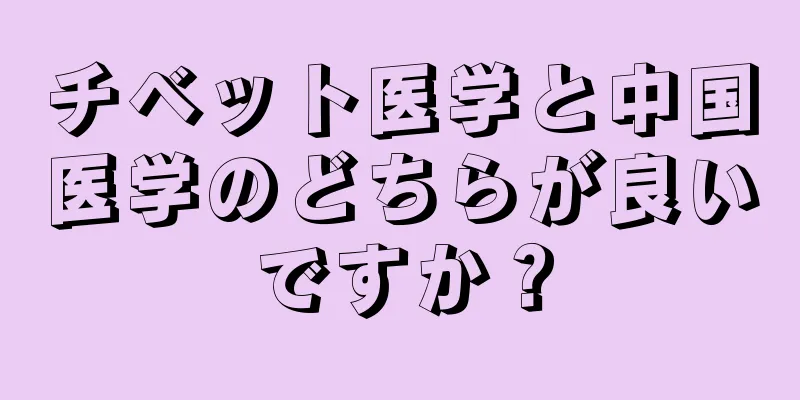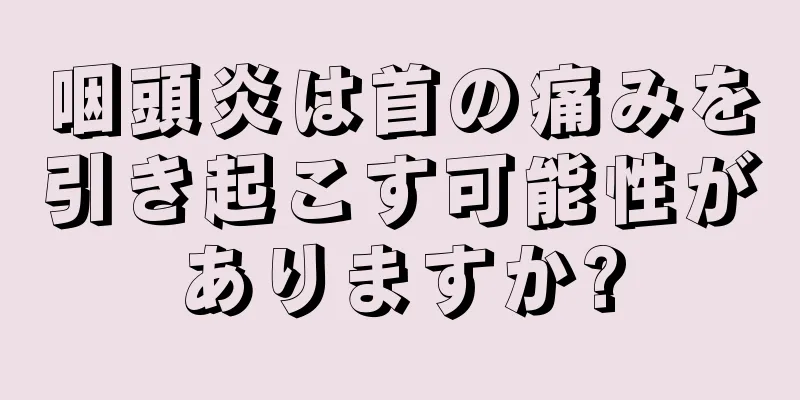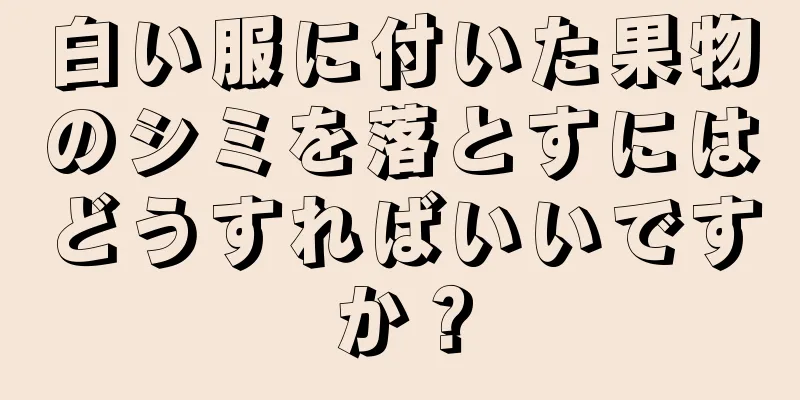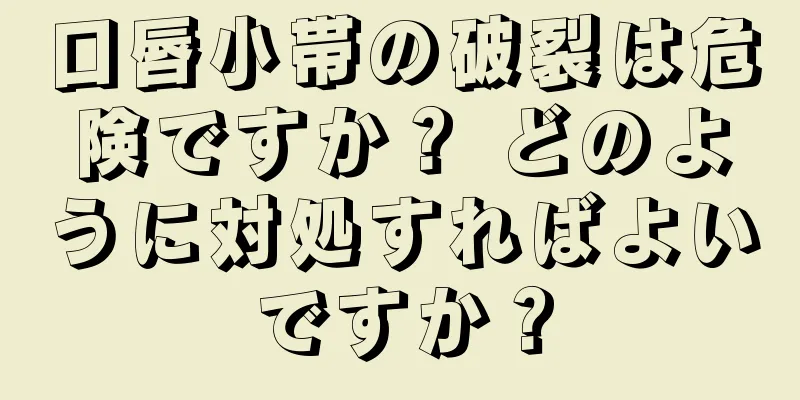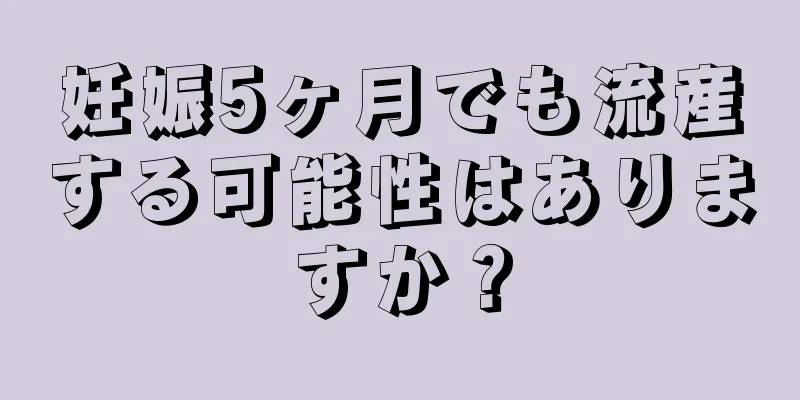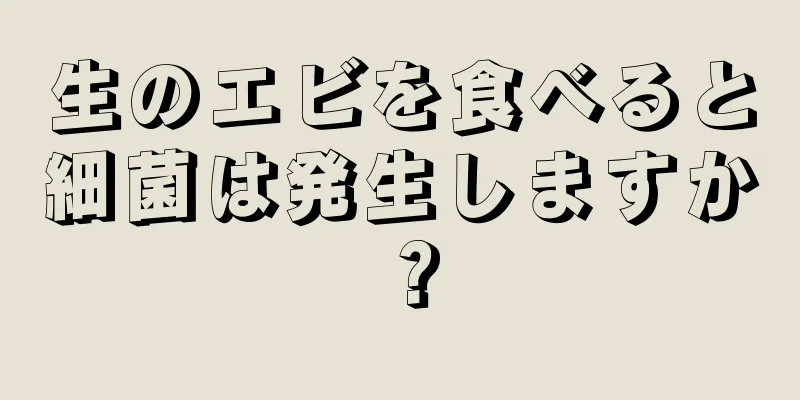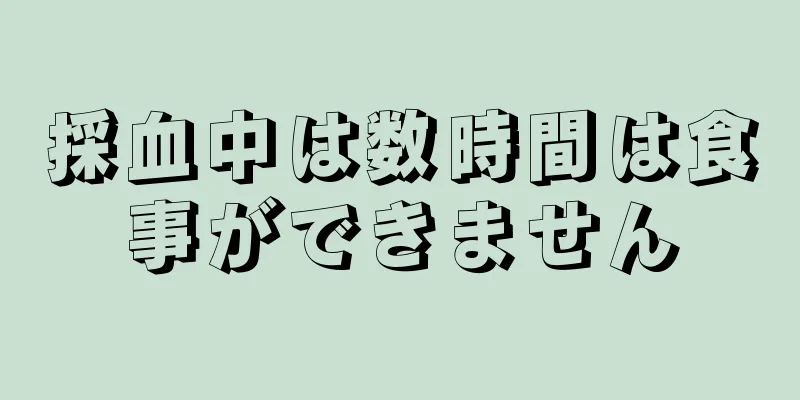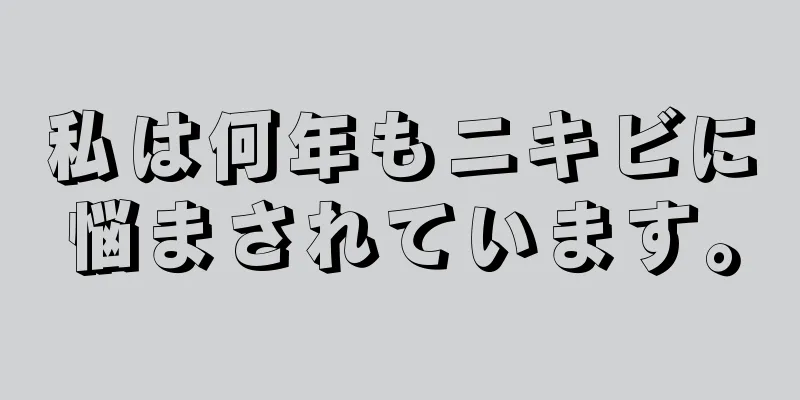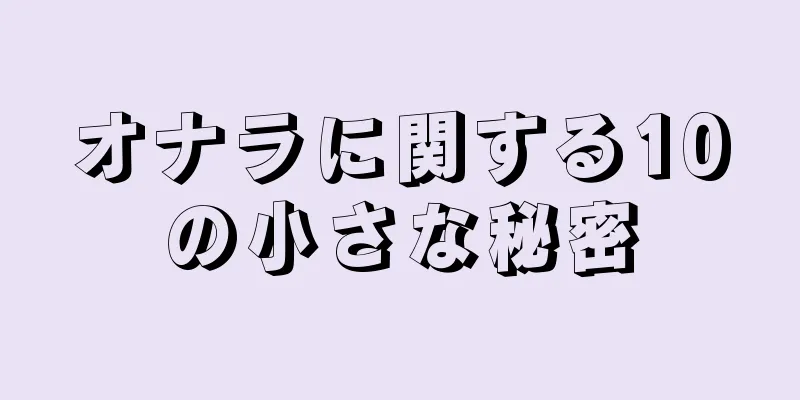ニコチンアミド硫酸塩を服用する際の注意事項は何ですか?
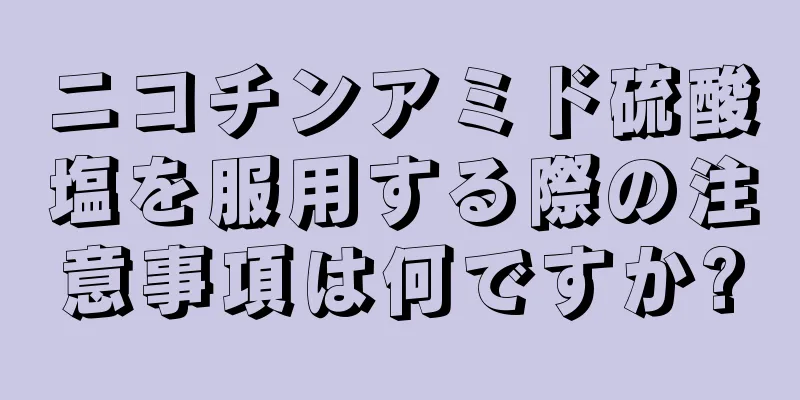
|
私たちの日常生活には、大腸菌、赤痢菌、プロテウスなど、多くの種類の細菌が存在します。これらの細菌が人体に入ると、敗血症、気管支炎、肺炎など多くの病気を引き起こします。治療方法が正しくないと、症状が悪化します。硫酸マイクロマイシンはこれらの病気を効果的に治療できます。では、硫酸マイクロマイシンの注意事項は何でしょうか? まず、メトロニダゾール硫酸塩を服用する際の注意事項は何ですか?この製品は主に大腸菌、クレブシエラ、プロテウス、エンテロバクター、セラチア、緑膿菌などのグラム陰性細菌による呼吸器、尿路、腹腔、外傷感染症に使用され、敗血症にも使用できます。 第二に、用法・用量:希釈後、筋肉内注射または点滴静注。成人:筋肉内注射:1回60~80mg、必要に応じて120mgまで、1日2~3回。点滴静注:1回60mg(1回2バイアル)を塩化ナトリウム注射液100mlに加えて一定速度で点滴し、点滴は1時間以内に完了する。小児:体重1kgあたり3~4mgを2~3回に分けて服用します。 3 番目に、副作用として、一般的な難聴、耳鳴りまたは耳の閉塞感 (聴器毒性)、血尿、排尿頻度の大幅な減少または尿量の減少、食欲不振、極度の喉の渇き (腎毒性)、歩行の不安定さ、めまい (聴器毒性、前庭効果)、吐き気または嘔吐 (聴器毒性、前庭効果、腎毒性) が挙げられます。 2. まれに、視覚障害(視神経炎)、呼吸困難、眠気、極度の脱力感(神経筋遮断)、発疹などのアレルギー反応、血球数の変化、肝機能の変化、胃腸反応、注射部位の痛み、結節、静脈炎などが起こることがあります。 3. アナフィラキシーショックは非常にまれです。 メトロニダゾール硫酸塩の注意事項は何ですか? 腎不全、肝機能異常、前庭機能または難聴、脱水症、重症筋無力症またはパーキンソン病の患者、および高齢者には慎重に使用する必要があります。投薬期間は一般的に 14 日を超えないようにしてください。投薬を継続する必要がある場合は、聴覚器官と腎臓の機能を注意深く監視する必要があります。交差アレルギー: ストレプトマイシンやゲンタマイシンなどのアミノグリコシド系抗生物質にアレルギーのある患者は、この製品にもアレルギーを起こす可能性があります。条件が許せば、治療中は血中薬物濃度をモニタリングし、それに応じて投与量を調整する必要があります。血中薬物濃度を測定できない場合は、特に腎機能障害、未熟児、新生児、乳児または高齢者、ショック、心不全、腹水または重度の脱水症の患者の場合は、測定されたクレアチニンクリアランスに応じて投与量を調整する必要があります。この製品は通常、筋肉内注射専用です。希釈後、静脈内注射することもできますが、神経筋遮断および呼吸抑制を避けるため、静脈内注射はしないでください。本製品を長期使用すると薬剤耐性菌の過剰増殖を引き起こす可能性があります。腎尿細管の損傷を軽減するために、患者には十分な水分を与える必要があります。 |
>>: ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠を使用する際に注意すべきことは何ですか?
推薦する
不眠症は神経衰弱ですか?
不眠症はよくある現象です。心配事や大きなプレッシャーが不眠症の原因となります。しかし、この状態をうま...
スクワットは性的パフォーマンスを向上させることができますか?
多くの人は普段からフィットネスの習慣を持っています。フィットネスには多くの種類があります。スクワット...
AMZ123はあらゆる困難にもかかわらず河南省の支援に駆けつけます!国境を越えた企業寄付情報をまとめました!
最近、集中豪雨の影響で、鄭州、新郷、開封など河南省の多くの場所で洪水が発生し、河南省の人々の生命と財...
ホルムアルデヒドを除去する最良の方法は何ですか?
ホルムアルデヒドについては、多くの人がよく知っています。家具や装飾材にホルムアルデヒドが含まれている...
慢性虫垂炎の治療のための伝統的な漢方薬の処方
慢性虫垂炎の発生率は非常に高く、その発生につながる要因は数多くあります。慢性虫垂炎の症状が比較的軽度...
グリセリンと白酢の副作用
圧縮フェイシャルマスクは、安価で使いやすく、肌に潤いを与える効果がより顕著であるため、美容市場でます...
歯磨き粉でカビのシミを取り除く方法
私たちは毎日歯磨き粉を使います。朝と夜の歯磨きのときに歯磨き粉を使います。歯磨き粉は口の中を効果的に...
足の爪が根元から白くなる
足の爪は人々の健康に大きな役割を果たしていませんが、足の爪に病気の症状が現れると、人々に非常に苦痛な...
咳をすると腹痛が起こる
腹痛は非常によくある現象です。痛みの特徴は異なり、考えられる原因も異なります。持続的な痛み、間接的な...
遺伝子組み換え食品の危険性は何ですか?
実際、私たちの生活の中で遺伝子組み換えという言葉を聞くことはほとんどないかもしれませんが、私たちが食...
羅布麻真珠茶の効果は何ですか?
羅布麻真珠茶には、清熱、利尿、肝鎮静、精神安定などの効果があり、動悸やめまいなどの症状を和らげること...
体に水ぶくれができる
体に水疱ができることはよくある現象で、体に水疱ができる原因は様々です。水疱の具体的な原因によって、摩...
衣服についた薬の汚れを落とす方法
日常生活では、服、特に赤ちゃんの服に薬の汚れが付く状況によく遭遇します。このような状況に遭遇した場合...
抗炎症生理食塩水のCTスキャン後、肺がんは小さくなりますか?
がんとなると、誰もが恐れます。がんは治療が難しいだけでなく、患者に大きな苦痛をもたらします。肺がんは...
5つの舌の表現はあなたが怒っている場所を示します
伝統的な中国医学では「観察、聴診、問診、触診」を重視しており、その中でも「観察」による診断は最も学び...